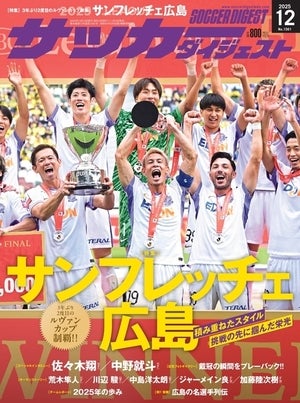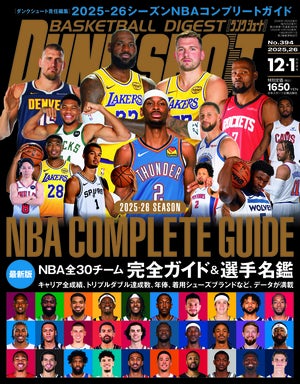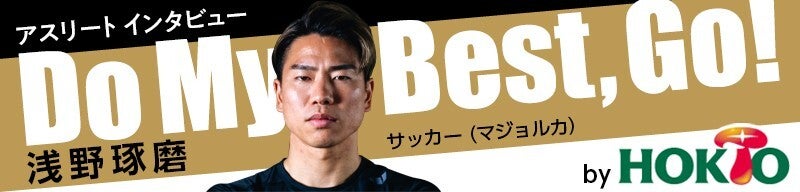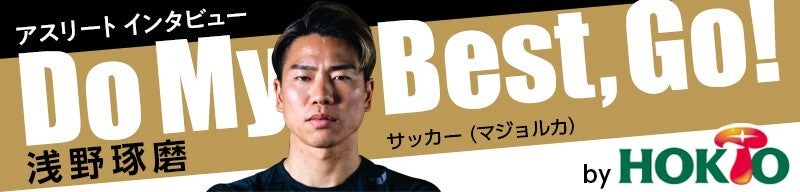開幕からちょうど10節を終えたセリエAは、近年稀に見る混戦模様となっている。なにしろ、勝点21で首位に立つナポリ、それをわずか1ポイント差で追うインテル、ミラン、ローマと、4チームがダンゴ状態で先頭グループを形成しているのだ。
しかもそのすぐ下には勝点18のボローニャとユベントス、勝点17のコモが続いており、首位から5ポイント差に7チームが固まっている。すでにアーセナル、レアル・マドリー、バイエルンが2位に5~6ポイント差をつけて独走体制を築いているプレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガとは対照的だ。
このトップ7の中で最も大きなサプライズは、ここまで4勝5分け1敗(勝点17)で7位に食い込んでいるコモだろう。スイスとの国境に近い人口10万人にも満たない小都市を本拠地とする昇格2年目のプロビンチャーレ(地方都市の中小クラブ)としては、目を見張る躍進である。
チームを率いるのは「あの」セスク・ファブレガス。アーセナル、バルセロナ、チェルシーで華やかな選手キャリアを送った後、モナコを経て最後に移籍したセリエBのコモで現役生活を終えて指導者に転身し、1年目のシーズン途中で早くもU-19からトップチーム監督にステップアップ。すぐにセリエA昇格を勝ち取ると、昨シーズンは昇格1年目で10位という好成績でフィニッシュして大きな注目と賞賛を集めた。
2年目の今シーズンも、開幕からの10試合でラツィオ、ユベントスを破り、アタランタ、ナポリと引き分けるなど、上位陣とも互角に渡り合って一桁順位をキープしている。
もちろん、一介のプロビンチャーレが監督の手腕だけでこれだけの結果を残せるほど、セリエAは甘い世界ではない。コモのオーナーは、世界の長者番付でトップ100に名を連ねるハルトノ家が保有するインドネシアの巨大財閥ジャルムグループ。
そこから派遣されてクラブの会長を務めるメディアプロデューサーのミルワン・スワルソは、元々イタリア屈指の観光リゾート地だったコモ湖とサッカーを結びつけることで、コモを「世界で最も魅力的でプレミアムなサッカー観光地にする」という壮大なビジョンを描き、ソフト、ハードの両面に戦略的かつ積極的な投資を続けている。
昇格1年目の昨シーズンは夏・冬合わせて1億ユーロ(約177億円)近い金額を移籍マーケットに投下し、今夏もさらに1億ユーロを超える資金を費やして、チームの強化を図った。これはミラン、ユベントス、アタランタ、ナポリに次いでリーグ5位にあたる金額だ(インテルやローマよりも多い)。
注目すべきは、獲得した選手の大部分が、名前と実績のある即戦力ではなく、セスク監督自身がその目で選んだ、大きな伸びしろを残す欧州トップレベルの若きタレントであるところ。昨夏に獲得したMFニコ・パス、MFマキシモ・ペローネ、昨冬のFWアサネ・ディアオ、MFマクソンス・カクレ、DFアレックス・バジェ、今夏のFWヘスス・ロドリゲス、FWニコラス・キューン、MFマルティン・バトゥリナ、DFハコボ・ラモンらは、いずれも欧州ビッグクラブのスカウティングリストに名を連ねていた逸材である。
今シーズンはそこに、FWアルバロ・モラタ、DFジエゴ・カルロスという、ピッチ内外でリーダーシップを発揮できるベテランも加え、スカッド構成は若い(出場選手平均25.8歳はリーグで4番目に低い)ながら、振る舞いは十分に成熟したチームができ上がった。
基本フォーメーション(4-2-3-1)は以下の通り。
GK:ビュテ
DF:スモルチッチ、ラモン、ケンプ(D・カルロス)、バジェ
DMF:ペローネ、ダ・クーニャ(カクレ)
OMF:アダイ(キューン)、パス、J・ロドリゲス(ディアオ)
FW:モラタ(ドゥビカス)
セスクは、自らの眼鏡にかなった彼らタレントたちの能力を引き出し活かす、先鋭的なサッカーを見せている。アーセナルでアーセン・ヴェンゲル、バルセロナでジョゼップ・グアルディオラに師事しただけに、そのサッカーも彼らの影響が強いのではというイメージを持ちやすいが、それに即して言えば、テクニカルでありながら縦指向が強い攻撃は「ヴェンゲルのアーセナル」的であり、アグレッシブなゲーゲンプレッシングによる即時奪回を柱とする守備は「グアルディオラのバルセロナ」的だと言えるかもしれない。
逆に言えば、コモのサッカーは、横パスを多用してポゼッションでボールと地域を支配し、敵陣で戦うスペイン的なスタイルとは明らかに異なっているということだ。
それは、データにもはっきりと表われている。ここまで10試合の成績は4勝5分け1敗(勝点17)の7位だが、12得点はリーグで上から8番目で、最も多いインテル(24得点)の半分に留まっている一方、6失点はローマに次いでリーグ2位。躍進を支えているのは、攻撃力よりもむしろ守備力の高さだということになる。
それでもコモがいわゆる「守備的」なチームかと言えば、まったくそんなことはない。ボール支配率58.5%は、インテル、ローマ、ナポリに次いでリーグ4位。この数字は、ボール保持を通して試合の主導権を握って戦っていることを意味しており、その意味では「攻撃的」なチームだと言うことができる。
実際、コモは自陣に引きこもって相手の攻撃を受動的に受け止めるようなチームではまったくない。それとは正反対に、セリエAの中で最も能動的かつ攻撃的な守備を行なうチームだ。それをはっきりと表わしているのが、プレス強度の指標であるPPDA(守備アクション1回につき相手に許したパス数の平均)が6.86と、圧倒的リーグ1位の数字であること。
ボールを奪われたら間髪入れずに襲いかかって相手を囲み、一気に奪い返すアグレッシブなゲーゲンプレッシング、相手のビルドアップに対して前線からマンツーマンで襲いかかる超攻撃的ハイプレスは、コモの最大の武器と言っていい。
自陣に引いて相手の攻撃を受動的に受け止めるのではなく、敵陣で前に出て相手に襲いかかり能動的にボールを奪回する――。ボール非保持の局面においても「攻撃的な」姿勢を貫くところに、セスク監督のサッカー哲学がはっきりと表れている。象徴的なのは、チームで最もデュエル数、タックル数が多いのがトップ下のパスだという事実だ。
1試合平均デュエル数14.2はなんとリーグ全体でトップ、同タックル数3.04も7位。ボールを持てば華麗なプレーを連発するセリエA屈指のファンタジスタが、守備の指標でこれだけの数字を記録しているところにこそ、他チームにはない個性がはっきり表われている。
しかもそのすぐ下には勝点18のボローニャとユベントス、勝点17のコモが続いており、首位から5ポイント差に7チームが固まっている。すでにアーセナル、レアル・マドリー、バイエルンが2位に5~6ポイント差をつけて独走体制を築いているプレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガとは対照的だ。
このトップ7の中で最も大きなサプライズは、ここまで4勝5分け1敗(勝点17)で7位に食い込んでいるコモだろう。スイスとの国境に近い人口10万人にも満たない小都市を本拠地とする昇格2年目のプロビンチャーレ(地方都市の中小クラブ)としては、目を見張る躍進である。
チームを率いるのは「あの」セスク・ファブレガス。アーセナル、バルセロナ、チェルシーで華やかな選手キャリアを送った後、モナコを経て最後に移籍したセリエBのコモで現役生活を終えて指導者に転身し、1年目のシーズン途中で早くもU-19からトップチーム監督にステップアップ。すぐにセリエA昇格を勝ち取ると、昨シーズンは昇格1年目で10位という好成績でフィニッシュして大きな注目と賞賛を集めた。
2年目の今シーズンも、開幕からの10試合でラツィオ、ユベントスを破り、アタランタ、ナポリと引き分けるなど、上位陣とも互角に渡り合って一桁順位をキープしている。
もちろん、一介のプロビンチャーレが監督の手腕だけでこれだけの結果を残せるほど、セリエAは甘い世界ではない。コモのオーナーは、世界の長者番付でトップ100に名を連ねるハルトノ家が保有するインドネシアの巨大財閥ジャルムグループ。
そこから派遣されてクラブの会長を務めるメディアプロデューサーのミルワン・スワルソは、元々イタリア屈指の観光リゾート地だったコモ湖とサッカーを結びつけることで、コモを「世界で最も魅力的でプレミアムなサッカー観光地にする」という壮大なビジョンを描き、ソフト、ハードの両面に戦略的かつ積極的な投資を続けている。
昇格1年目の昨シーズンは夏・冬合わせて1億ユーロ(約177億円)近い金額を移籍マーケットに投下し、今夏もさらに1億ユーロを超える資金を費やして、チームの強化を図った。これはミラン、ユベントス、アタランタ、ナポリに次いでリーグ5位にあたる金額だ(インテルやローマよりも多い)。
注目すべきは、獲得した選手の大部分が、名前と実績のある即戦力ではなく、セスク監督自身がその目で選んだ、大きな伸びしろを残す欧州トップレベルの若きタレントであるところ。昨夏に獲得したMFニコ・パス、MFマキシモ・ペローネ、昨冬のFWアサネ・ディアオ、MFマクソンス・カクレ、DFアレックス・バジェ、今夏のFWヘスス・ロドリゲス、FWニコラス・キューン、MFマルティン・バトゥリナ、DFハコボ・ラモンらは、いずれも欧州ビッグクラブのスカウティングリストに名を連ねていた逸材である。
今シーズンはそこに、FWアルバロ・モラタ、DFジエゴ・カルロスという、ピッチ内外でリーダーシップを発揮できるベテランも加え、スカッド構成は若い(出場選手平均25.8歳はリーグで4番目に低い)ながら、振る舞いは十分に成熟したチームができ上がった。
基本フォーメーション(4-2-3-1)は以下の通り。
GK:ビュテ
DF:スモルチッチ、ラモン、ケンプ(D・カルロス)、バジェ
DMF:ペローネ、ダ・クーニャ(カクレ)
OMF:アダイ(キューン)、パス、J・ロドリゲス(ディアオ)
FW:モラタ(ドゥビカス)
セスクは、自らの眼鏡にかなった彼らタレントたちの能力を引き出し活かす、先鋭的なサッカーを見せている。アーセナルでアーセン・ヴェンゲル、バルセロナでジョゼップ・グアルディオラに師事しただけに、そのサッカーも彼らの影響が強いのではというイメージを持ちやすいが、それに即して言えば、テクニカルでありながら縦指向が強い攻撃は「ヴェンゲルのアーセナル」的であり、アグレッシブなゲーゲンプレッシングによる即時奪回を柱とする守備は「グアルディオラのバルセロナ」的だと言えるかもしれない。
逆に言えば、コモのサッカーは、横パスを多用してポゼッションでボールと地域を支配し、敵陣で戦うスペイン的なスタイルとは明らかに異なっているということだ。
それは、データにもはっきりと表われている。ここまで10試合の成績は4勝5分け1敗(勝点17)の7位だが、12得点はリーグで上から8番目で、最も多いインテル(24得点)の半分に留まっている一方、6失点はローマに次いでリーグ2位。躍進を支えているのは、攻撃力よりもむしろ守備力の高さだということになる。
それでもコモがいわゆる「守備的」なチームかと言えば、まったくそんなことはない。ボール支配率58.5%は、インテル、ローマ、ナポリに次いでリーグ4位。この数字は、ボール保持を通して試合の主導権を握って戦っていることを意味しており、その意味では「攻撃的」なチームだと言うことができる。
実際、コモは自陣に引きこもって相手の攻撃を受動的に受け止めるようなチームではまったくない。それとは正反対に、セリエAの中で最も能動的かつ攻撃的な守備を行なうチームだ。それをはっきりと表わしているのが、プレス強度の指標であるPPDA(守備アクション1回につき相手に許したパス数の平均)が6.86と、圧倒的リーグ1位の数字であること。
ボールを奪われたら間髪入れずに襲いかかって相手を囲み、一気に奪い返すアグレッシブなゲーゲンプレッシング、相手のビルドアップに対して前線からマンツーマンで襲いかかる超攻撃的ハイプレスは、コモの最大の武器と言っていい。
自陣に引いて相手の攻撃を受動的に受け止めるのではなく、敵陣で前に出て相手に襲いかかり能動的にボールを奪回する――。ボール非保持の局面においても「攻撃的な」姿勢を貫くところに、セスク監督のサッカー哲学がはっきりと表れている。象徴的なのは、チームで最もデュエル数、タックル数が多いのがトップ下のパスだという事実だ。
1試合平均デュエル数14.2はなんとリーグ全体でトップ、同タックル数3.04も7位。ボールを持てば華麗なプレーを連発するセリエA屈指のファンタジスタが、守備の指標でこれだけの数字を記録しているところにこそ、他チームにはない個性がはっきり表われている。
関連記事
- CLイタリア勢の現状と展望 インテルが唯一の3連勝、アタランタ、ナポリ、ユベントスは正念場「ラスト30mを攻略する有効な攻め手がない状況」【現地発コラム】
- 予選2位以上確定のイタリア代表、プレーオフの相手は“運命のいたずら”?「乗り越えられないようなら、W杯に出場する資格はない」【現地発コラム】
- データを用いてナポリ、ローマ、ユベントスを徹底分析「根付きつつあるガスペリーニ哲学」「トゥドル監督にとって最優先の課題は」セリエA序盤戦総括(前編)【現地発コラム】
- データを用いてミラン、インテルを徹底分析「アッレーグリとキブのスタイルは、まったくの対極」「伸びしろが最も大きく見えるのは」セリエA序盤戦総括(後編)【現地発コラム】
- セリエA首位浮上の好調ミラン「チーム全体の構造が安定した」要因と「改善・向上の余地が残されている」局面とは【現地発コラム】