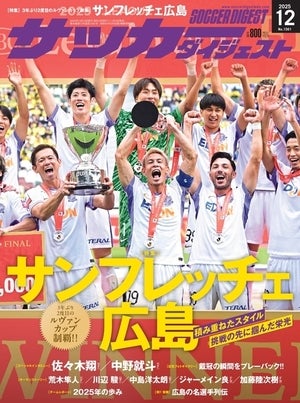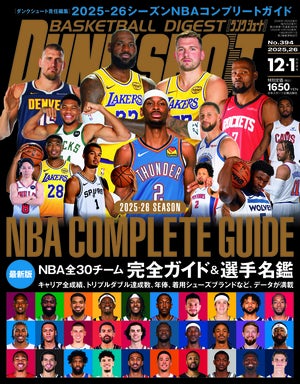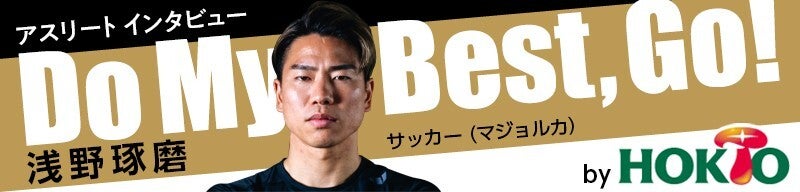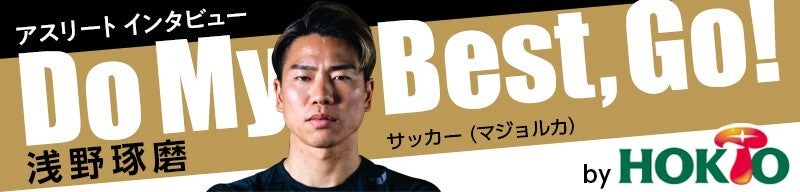コモの「能動的かつ攻撃的な守備」がを示すデータはそれだけに留まらない。1試合平均のタックル数(18.8)、タックル勝利数(10.9)はいずれもリーグトップ、ファウル数(15.9)、イエローカード数(2.4)はリーグ2位の数字だ。
ここにも、コンパクトな陣形を高い位置まで押し上げてボールホルダーに常に激しいプレッシャーをかけ、抜かれそうになった場合はファウルも辞さないという、きわめてアグレッシブな姿勢が反映されている。高く押し上げた最終ラインの背後は、ゴールキーパーが「スイーパー」としてケアする仕組み。GKによるペナルティーエリア外での守備アクション数(1試合平均2.5回)も、リーグで最も多い数字だ。
保守的なローブロック守備が今なお主流を占めるセリエAにおいても、近年はアグレッシブに前に出る能動的な守備戦術を採用するチームが少しずつ増え始めている。しかしその多くは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が率いていた昨シーズンまでのアタランタ、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督のフィオレンティーナやボローニャのように得点も多いが失点も多い、いわゆる「出入りの激しい」サッカーをするチームだった。
それに対してコモは、「能動的かつ攻撃的な守備」を実践しながら、失点をリーグ2位に抑えることに成功している。ややもするとパスやペローネに象徴される攻撃面にスポットライトが当たりやすいが、躍進を支えているのがむしろ守備の局面であることは、もっと注目されていい。
しかしもちろん、コモのサッカーの「魅力」が守備よりも攻撃の局面にあることは動かしがたい事実だ。GKジャン・ビュテを積極的に組み込み、動的なポジションチェンジを活かし長短のパスを的確に使い分けて前進するビルドアップ、ペローネ、MFルーカス・ダ・クーニャ(カクレ)の2ボランチを核とするワンタッチ、ツータッチの流麗なパス交換、2ライン(MFとDF)間からアイデア溢れるドリブルやスルーパス、そしてシュートで決定的な場面を作り出すパスのファンタジアは、見る者を魅了する。
後方からのビルドアップにおいて、きわめて重要な役割を担っているのが、30歳のフランス人守護神のビュテ。ゴールキーピングは平均レベルでしかないが、左右両足を効果的に使い分ける長短のパスワーク、状況を的確に読み取りプレーの方向性とタイミングを判断するプレービジョンといった「11人目のフィールドプレーヤー」としてのクオリティーは、MF並みの水準にある。
左右に開いた2CBの間に入ってビルドアップの第1列を形成し、プレッシャーを受けても動じないどころか、自らボールをさらしてプレッシャーを誘引し、相手のプレッシャーラインを超えるパスコースを作り出すことすらやってのける。
このビュテを起点とする後方からのビルドアップは、第1列にGKと2CB、第2列にボランチと左右SBが並ぶ3+4ユニットが基本。ゴールキックやGKからのビルドアップ時には、2ボランチが自陣ペナルティーエリア付近まで下がるのが大きな特徴だ。
昨今のセリエAで主流になってきているマンツーマンハイプレスの原則に従えば、2ボランチをマークする相手のボランチも大きく前進して来ることになる。これによってビルドアップの起点となるゴール前の人口密度が高くなる一方、ハーフウェーライン付近にポジションを取る4人のアタッカー陣(とそれをマークする相手DF陣)との間には、広大なスペースが生まれることになる。
コモは後方でのパス回しを通じて、GKビュテが作り出す相手のプレスに対する「プラス1」の数的優位を生かしてフリーマンを作り出すと同時に、そのタイミングで前線からライン間の広いスペースに降りてくるトップ下のパスやCFモラタに縦パスを送り込み、プレスに出てきた相手6人を置き去りにして一気に前進、そのままゴールに迫る「疑似カウンター」的な場面をしばしば作り出す。
自陣ファーストサードに7対6のスモールフィールドを作り出すこのビルドアップは、ボールを奪われれば即致命的なチャンスにつながるハイリスクな選択だ。
しかしコモはGKビュテに加えて、CBラモン、ボランチのペローネ、ダ・クーニャと、狭いスペースでプレッシャーを受けても正確にパスをつなげるテクニックと戦術眼を備えた選手を揃え、どんなに厳しいプレスを受けても怯むことなく自信を持って攻撃を組み立てる。プレスをかわして前線にボールを送り込めば、そこからは広いスペースを使って4対4の数的均衡でスピードに乗った「疑似カウンター」が可能になる。これはコモの大きな武器のひとつだ。
もちろん、相手が常にハイプレスを仕掛けてくるわけではない。相手が受けに回ってビルドアップの開始点がミドルサードまで上がった場合には、左SBのバジェが早いタイミングで前線まで上がることで、第1列に右SBと2CB、第2列に2ボランチという3+2ユニットを形成し、前線ではピッチの幅一杯に5人が広がることで、ポジショナルプレーの典型ともいうべき3-2-5の配置を取る。
ここから、ワンタッチ、ツータッチのリズミカルなパス交換に、大きなサイドチェンジや裏へのロングボールを効果的に交えて、相手の守備ブロック攻略にかかるわけだ。
ここで主役を演じるのがトップ下のパス。元アルゼンチン代表DFを父(パブロ・パス)に持ちスペインで生まれ育ったこの21歳のファンタジスタは、186センチ、74キロの恵まれた体躯と強力かつ繊細な左足のテクニックを駆使して、2ライン間の密集の中でも相手のプレッシャーをはねのけ、決定的な場面を作り出す。
開幕10試合の決定機創出数53回は、ルカ・モドリッチ(ミラン)、フェデリコ・ディマルコ(インテル)、ケナン・ユルディズ(ユベントス)を上回ってリーグトップ。ドリブル試行数と成功数はいずれもリーグ3位、シュート数リーグ2位、枠内シュート数3位、そして何よりゴールとアシストの合計(4+4)でリーグトップと、フィニッシュにかかわる攻撃のあらゆる指標で最高レベルの数字を叩き出している。
しかも、すでに見た通りデュエル数とタックル数でもリーグトップと、守備でも決定的な貢献を果たしているのだから、これはもうモンスター級のタレントである。
とはいえ、チームとして見るとコモの攻撃のデータは、それほど傑出しているわけではない。12得点はリーグ8位、1試合平均のゴール期待値(xG)1.22はリーグ10位、ファイナルサードやペナルティーエリアへのパス本数や侵入数もリーグで7~10位と、攻撃のボリューム自体はそれほど大きいとは言えない。
ゾーン別のボールタッチ数を見ても、ファーストサード、ミドルサードではリーグ3位だが、ファイナルサードではリーグ7位。中盤までを支配しながら、ラスト30mの攻略はパスの傑出した個人能力に依存している現状が浮かび上がってくる。
これは逆に見れば、CFモラタを筆頭に、右ウイングのFWジェイデン・アダイ、キューン、左ウイングのJ・ロドリゲスといった前線の新戦力、そして故障から復帰した昨シーズンの主力ディアオらアタッカー陣がチームと戦術に馴染み、組織の中で本来の力を発揮するようになれば、さらなる成長が期待できるということでもある。
20代前半と伸び盛りのタレントが大半を占める若いチームだということも含めて、コモはまだまだ大きな可能性を秘めている。このままトップグループに大きく離されることなく後半戦を迎えることができれば、ヨーロッパリーグ出場権争いはもちろん、チャンピオンズリーグ出場権を争うトップ4に迫ることすら不可能ではないかもしれない。そんな期待を抱かせるだけの魅力的なチームであることだけは確かである。
文●片野道郎
【動画】最新試合のナポリ戦、2-0で勝利したユベントス戦のダイジェスト!
ここにも、コンパクトな陣形を高い位置まで押し上げてボールホルダーに常に激しいプレッシャーをかけ、抜かれそうになった場合はファウルも辞さないという、きわめてアグレッシブな姿勢が反映されている。高く押し上げた最終ラインの背後は、ゴールキーパーが「スイーパー」としてケアする仕組み。GKによるペナルティーエリア外での守備アクション数(1試合平均2.5回)も、リーグで最も多い数字だ。
保守的なローブロック守備が今なお主流を占めるセリエAにおいても、近年はアグレッシブに前に出る能動的な守備戦術を採用するチームが少しずつ増え始めている。しかしその多くは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が率いていた昨シーズンまでのアタランタ、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督のフィオレンティーナやボローニャのように得点も多いが失点も多い、いわゆる「出入りの激しい」サッカーをするチームだった。
それに対してコモは、「能動的かつ攻撃的な守備」を実践しながら、失点をリーグ2位に抑えることに成功している。ややもするとパスやペローネに象徴される攻撃面にスポットライトが当たりやすいが、躍進を支えているのがむしろ守備の局面であることは、もっと注目されていい。
しかしもちろん、コモのサッカーの「魅力」が守備よりも攻撃の局面にあることは動かしがたい事実だ。GKジャン・ビュテを積極的に組み込み、動的なポジションチェンジを活かし長短のパスを的確に使い分けて前進するビルドアップ、ペローネ、MFルーカス・ダ・クーニャ(カクレ)の2ボランチを核とするワンタッチ、ツータッチの流麗なパス交換、2ライン(MFとDF)間からアイデア溢れるドリブルやスルーパス、そしてシュートで決定的な場面を作り出すパスのファンタジアは、見る者を魅了する。
後方からのビルドアップにおいて、きわめて重要な役割を担っているのが、30歳のフランス人守護神のビュテ。ゴールキーピングは平均レベルでしかないが、左右両足を効果的に使い分ける長短のパスワーク、状況を的確に読み取りプレーの方向性とタイミングを判断するプレービジョンといった「11人目のフィールドプレーヤー」としてのクオリティーは、MF並みの水準にある。
左右に開いた2CBの間に入ってビルドアップの第1列を形成し、プレッシャーを受けても動じないどころか、自らボールをさらしてプレッシャーを誘引し、相手のプレッシャーラインを超えるパスコースを作り出すことすらやってのける。
このビュテを起点とする後方からのビルドアップは、第1列にGKと2CB、第2列にボランチと左右SBが並ぶ3+4ユニットが基本。ゴールキックやGKからのビルドアップ時には、2ボランチが自陣ペナルティーエリア付近まで下がるのが大きな特徴だ。
昨今のセリエAで主流になってきているマンツーマンハイプレスの原則に従えば、2ボランチをマークする相手のボランチも大きく前進して来ることになる。これによってビルドアップの起点となるゴール前の人口密度が高くなる一方、ハーフウェーライン付近にポジションを取る4人のアタッカー陣(とそれをマークする相手DF陣)との間には、広大なスペースが生まれることになる。
コモは後方でのパス回しを通じて、GKビュテが作り出す相手のプレスに対する「プラス1」の数的優位を生かしてフリーマンを作り出すと同時に、そのタイミングで前線からライン間の広いスペースに降りてくるトップ下のパスやCFモラタに縦パスを送り込み、プレスに出てきた相手6人を置き去りにして一気に前進、そのままゴールに迫る「疑似カウンター」的な場面をしばしば作り出す。
自陣ファーストサードに7対6のスモールフィールドを作り出すこのビルドアップは、ボールを奪われれば即致命的なチャンスにつながるハイリスクな選択だ。
しかしコモはGKビュテに加えて、CBラモン、ボランチのペローネ、ダ・クーニャと、狭いスペースでプレッシャーを受けても正確にパスをつなげるテクニックと戦術眼を備えた選手を揃え、どんなに厳しいプレスを受けても怯むことなく自信を持って攻撃を組み立てる。プレスをかわして前線にボールを送り込めば、そこからは広いスペースを使って4対4の数的均衡でスピードに乗った「疑似カウンター」が可能になる。これはコモの大きな武器のひとつだ。
もちろん、相手が常にハイプレスを仕掛けてくるわけではない。相手が受けに回ってビルドアップの開始点がミドルサードまで上がった場合には、左SBのバジェが早いタイミングで前線まで上がることで、第1列に右SBと2CB、第2列に2ボランチという3+2ユニットを形成し、前線ではピッチの幅一杯に5人が広がることで、ポジショナルプレーの典型ともいうべき3-2-5の配置を取る。
ここから、ワンタッチ、ツータッチのリズミカルなパス交換に、大きなサイドチェンジや裏へのロングボールを効果的に交えて、相手の守備ブロック攻略にかかるわけだ。
ここで主役を演じるのがトップ下のパス。元アルゼンチン代表DFを父(パブロ・パス)に持ちスペインで生まれ育ったこの21歳のファンタジスタは、186センチ、74キロの恵まれた体躯と強力かつ繊細な左足のテクニックを駆使して、2ライン間の密集の中でも相手のプレッシャーをはねのけ、決定的な場面を作り出す。
開幕10試合の決定機創出数53回は、ルカ・モドリッチ(ミラン)、フェデリコ・ディマルコ(インテル)、ケナン・ユルディズ(ユベントス)を上回ってリーグトップ。ドリブル試行数と成功数はいずれもリーグ3位、シュート数リーグ2位、枠内シュート数3位、そして何よりゴールとアシストの合計(4+4)でリーグトップと、フィニッシュにかかわる攻撃のあらゆる指標で最高レベルの数字を叩き出している。
しかも、すでに見た通りデュエル数とタックル数でもリーグトップと、守備でも決定的な貢献を果たしているのだから、これはもうモンスター級のタレントである。
とはいえ、チームとして見るとコモの攻撃のデータは、それほど傑出しているわけではない。12得点はリーグ8位、1試合平均のゴール期待値(xG)1.22はリーグ10位、ファイナルサードやペナルティーエリアへのパス本数や侵入数もリーグで7~10位と、攻撃のボリューム自体はそれほど大きいとは言えない。
ゾーン別のボールタッチ数を見ても、ファーストサード、ミドルサードではリーグ3位だが、ファイナルサードではリーグ7位。中盤までを支配しながら、ラスト30mの攻略はパスの傑出した個人能力に依存している現状が浮かび上がってくる。
これは逆に見れば、CFモラタを筆頭に、右ウイングのFWジェイデン・アダイ、キューン、左ウイングのJ・ロドリゲスといった前線の新戦力、そして故障から復帰した昨シーズンの主力ディアオらアタッカー陣がチームと戦術に馴染み、組織の中で本来の力を発揮するようになれば、さらなる成長が期待できるということでもある。
20代前半と伸び盛りのタレントが大半を占める若いチームだということも含めて、コモはまだまだ大きな可能性を秘めている。このままトップグループに大きく離されることなく後半戦を迎えることができれば、ヨーロッパリーグ出場権争いはもちろん、チャンピオンズリーグ出場権を争うトップ4に迫ることすら不可能ではないかもしれない。そんな期待を抱かせるだけの魅力的なチームであることだけは確かである。
文●片野道郎
【動画】最新試合のナポリ戦、2-0で勝利したユベントス戦のダイジェスト!
関連記事
- CLイタリア勢の現状と展望 インテルが唯一の3連勝、アタランタ、ナポリ、ユベントスは正念場「ラスト30mを攻略する有効な攻め手がない状況」【現地発コラム】
- 予選2位以上確定のイタリア代表、プレーオフの相手は“運命のいたずら”?「乗り越えられないようなら、W杯に出場する資格はない」【現地発コラム】
- データを用いてナポリ、ローマ、ユベントスを徹底分析「根付きつつあるガスペリーニ哲学」「トゥドル監督にとって最優先の課題は」セリエA序盤戦総括(前編)【現地発コラム】
- データを用いてミラン、インテルを徹底分析「アッレーグリとキブのスタイルは、まったくの対極」「伸びしろが最も大きく見えるのは」セリエA序盤戦総括(後編)【現地発コラム】
- セリエA首位浮上の好調ミラン「チーム全体の構造が安定した」要因と「改善・向上の余地が残されている」局面とは【現地発コラム】