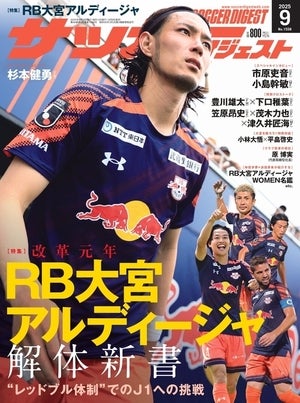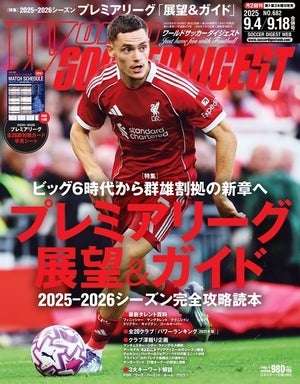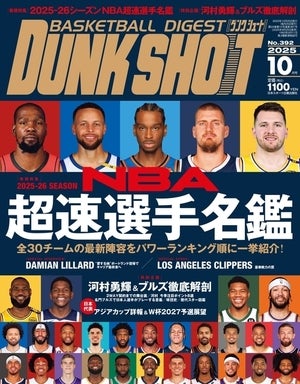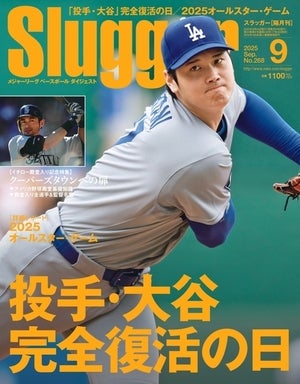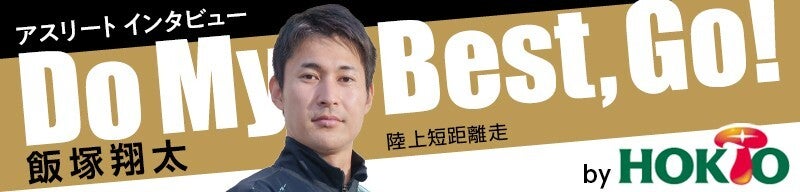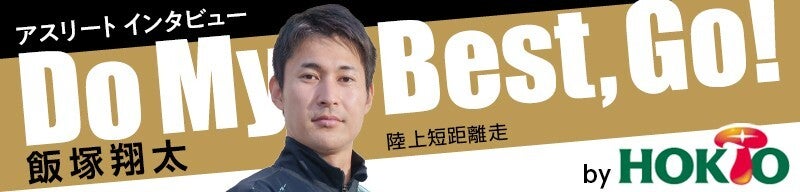■ビーチへ転向したきっかけ
――北京五輪の結果に対する思いは?
当時、男子代表チームは五輪に16年も行ってなくて、行くことが目標になっていたように感じていました。北京五輪出場が決まった瞬間は「次はメダルだ」と言っちゃいましたけど、そんなレベルじゃなかった。出場を決めるので精一杯というパフォーマンスだったんで、そこから五輪までの1か月半でどうコンディションを上げて、どう勝つのかが全くなかった。
「出れた、浮かれた、そのまま入っていく」という形になってしまったんです。五輪で勝つことを目標にしてないチームが本大会に出たらそういう結果になるんだなと痛感しましたね。
――北京に行ってグループ最下位になり、現実を突きつけられたんですね。
はい。今に比べるとインドアバレー界が少し鎖国的な感じだったので、僕的にはもっともっと挑戦してみてもよかったのかな。もう少し若かったらアグレッシブにチャレンジしても面白かったかんじゃないかと思います。
今は石川祐希選手とか西田有志選手とかインドアで海外に出ている選手はいますけど、15年くらい前だと「なんだあいつ」はみたいなことを言われる世界だったので時代は変わったなと。ちょっと早すぎたのかなとも感じます(笑)。
――そこで感じた不完全燃焼感が、ビーチに転向する原動力になったんですね?
そうですね。ビーチバレーボールは実力があれば、上に行けるチャンスもある世界。インドアは監督さんがいて、メンバーを選ぶ中で、候補に挙がらなかったら難しい。であれば、違うステージで挑戦して、ダメだったら納得がいく。そういう考えもありましたね。
――同じ頃、自国開催の東京五輪開催も決まりましたよね?
タイミング的に重なったのはあります。それまで真剣にバレーボールと向き合ってきて、勝つことのために物凄い犠牲を払ってきた。ケガもするし、ストレスもかかります。全ては勝利のためでした。
でも、第3者から見たら必ずしもそうは映らないこともある。否定的に捉えられることもあった。そういうことが重なって、「これで終わりたくないな」と強く感じた。自分が納得できることを最後までやり通して結果を出したいっていう思いが強かったんですよね。
――ビーチという新たに情熱をぶつけるものが見つかり、強いモチベーションを抱いたということですね?
ぶっちゃけていうと「ちくしょう、見てろよ」みたいな。「もう見返してやる」じゃないけど、半分はそういうのもありますよ。そうじゃなかったら、33歳という年齢でこの世界には来れないですよ。家族もいて。
――結婚してすぐの決断でしたからね?
そうですね。娘が1歳になるかならないかくらいで新たな世界に行くと決めたんで。その時は「保証なんかないから行くしかねえ」って感じですね。
写真提供:TOYOTA
――すぐに手ごたえはつかめたのですか?
いえ。行ったら「あれ、全然ダメじゃん」って(苦笑)。
――ビーチバレーボールはどんな難しさがありました?
ホント、大変でしたね。最初は週末に地域でプレーしてるおじさんに全く勝てない。
「ちょっと手抜いてるんじゃないですか」って言われたけど、こっちは必死にやっても勝てなかった。こっちで五輪目指すって決めたのに、こんなに下手なんだっていう現実に直面したんです。普通だったらプライドが許さないという気持ちになって、そこでやめてるんだろうなと。それくらい大変でした。
――地域のおじさんに勝てないとは、信じられないですね?
ホントに勝てなかったですね。適応が早い人は違うのかもしれませんが、僕がちょっと不器用な部分もあるんで。転向して最初の頃はそんな状態でしたね。
――どう這い上がった?
教えてくれる人からは全部教えてもらうし、自分のプレーをビデオで撮って客観的に見たりもした。少しでも自分が思い描く選手に近づけるようにコツコツと努力をするしかなかったですね。しぶとさがあったからできたのだと思います。
――コートやチームの人数の違い、暑さという異なる条件ものしかかります。
まず砂に慣れるまでに1年くらいはかかりました。ペアの選手が経験豊富でレベルの高い人だったので、自分が成長できたのはありました。思ったようなプレーをさせてもらえたし、力を引き出してもらえたので、本当に有難かったです。
もう1つ重要なのはビーチバレーの基本的なプレー。それをより深く意識して体に覚え込ませないといけなかった。根気強くやるんだと言い聞かせましたね。
――6人制とは違って、2人の場合はより連携を密にしないといけないですね。
はい。やっていけると思えたのは2年目かな。
そこからは徐々にレベルアップしていきました。最初からできる選手もいると思うんですけど、その場合はペア選手のレベルの高さに後押しされている場合が多い。自分ができたと勘違いしちゃうと成長がないまま終わるケースが多いというのが正直なところです。
――新たな自分自身に出会えた?
より自分自身に向き合うことができて、やりやすい競技だと感じましたね。
僕はもともとすごく我が強いんで、インドアの頃から「自分はこういうことをやって成長していくんだ」という確固たる信念がありました。五輪出場という目標があるのなら、チームの約束ごとさえ守っていたら、プロセスは人それぞれでいい。協調性がないというわけじゃないんですけど、そういう考え方だったんです。
でも、チームっていうのはみんなが右向け右でやる傾向が強いですよね。当時のインドアは僕が好き勝手やって責任を取ればいいという環境じゃなかった。今になると理解できますが、しっくりこないところがあったのは事実です。
その点、ビーチバレーボールは2人でやる競技なんで、自分自身が全ての責任を背負わなければいけない。悪ければ自分のせいということになりますし、プロセスに対して責任もってやれる環境にあるのは確か。そこは僕にとっては合うんじゃないかなと思いますね。
――北京五輪の結果に対する思いは?
当時、男子代表チームは五輪に16年も行ってなくて、行くことが目標になっていたように感じていました。北京五輪出場が決まった瞬間は「次はメダルだ」と言っちゃいましたけど、そんなレベルじゃなかった。出場を決めるので精一杯というパフォーマンスだったんで、そこから五輪までの1か月半でどうコンディションを上げて、どう勝つのかが全くなかった。
「出れた、浮かれた、そのまま入っていく」という形になってしまったんです。五輪で勝つことを目標にしてないチームが本大会に出たらそういう結果になるんだなと痛感しましたね。
――北京に行ってグループ最下位になり、現実を突きつけられたんですね。
はい。今に比べるとインドアバレー界が少し鎖国的な感じだったので、僕的にはもっともっと挑戦してみてもよかったのかな。もう少し若かったらアグレッシブにチャレンジしても面白かったかんじゃないかと思います。
今は石川祐希選手とか西田有志選手とかインドアで海外に出ている選手はいますけど、15年くらい前だと「なんだあいつ」はみたいなことを言われる世界だったので時代は変わったなと。ちょっと早すぎたのかなとも感じます(笑)。
――そこで感じた不完全燃焼感が、ビーチに転向する原動力になったんですね?
そうですね。ビーチバレーボールは実力があれば、上に行けるチャンスもある世界。インドアは監督さんがいて、メンバーを選ぶ中で、候補に挙がらなかったら難しい。であれば、違うステージで挑戦して、ダメだったら納得がいく。そういう考えもありましたね。
――同じ頃、自国開催の東京五輪開催も決まりましたよね?
タイミング的に重なったのはあります。それまで真剣にバレーボールと向き合ってきて、勝つことのために物凄い犠牲を払ってきた。ケガもするし、ストレスもかかります。全ては勝利のためでした。
でも、第3者から見たら必ずしもそうは映らないこともある。否定的に捉えられることもあった。そういうことが重なって、「これで終わりたくないな」と強く感じた。自分が納得できることを最後までやり通して結果を出したいっていう思いが強かったんですよね。
――ビーチという新たに情熱をぶつけるものが見つかり、強いモチベーションを抱いたということですね?
ぶっちゃけていうと「ちくしょう、見てろよ」みたいな。「もう見返してやる」じゃないけど、半分はそういうのもありますよ。そうじゃなかったら、33歳という年齢でこの世界には来れないですよ。家族もいて。
――結婚してすぐの決断でしたからね?
そうですね。娘が1歳になるかならないかくらいで新たな世界に行くと決めたんで。その時は「保証なんかないから行くしかねえ」って感じですね。

写真提供:TOYOTA
――すぐに手ごたえはつかめたのですか?
いえ。行ったら「あれ、全然ダメじゃん」って(苦笑)。
――ビーチバレーボールはどんな難しさがありました?
ホント、大変でしたね。最初は週末に地域でプレーしてるおじさんに全く勝てない。
「ちょっと手抜いてるんじゃないですか」って言われたけど、こっちは必死にやっても勝てなかった。こっちで五輪目指すって決めたのに、こんなに下手なんだっていう現実に直面したんです。普通だったらプライドが許さないという気持ちになって、そこでやめてるんだろうなと。それくらい大変でした。
――地域のおじさんに勝てないとは、信じられないですね?
ホントに勝てなかったですね。適応が早い人は違うのかもしれませんが、僕がちょっと不器用な部分もあるんで。転向して最初の頃はそんな状態でしたね。
――どう這い上がった?
教えてくれる人からは全部教えてもらうし、自分のプレーをビデオで撮って客観的に見たりもした。少しでも自分が思い描く選手に近づけるようにコツコツと努力をするしかなかったですね。しぶとさがあったからできたのだと思います。
――コートやチームの人数の違い、暑さという異なる条件ものしかかります。
まず砂に慣れるまでに1年くらいはかかりました。ペアの選手が経験豊富でレベルの高い人だったので、自分が成長できたのはありました。思ったようなプレーをさせてもらえたし、力を引き出してもらえたので、本当に有難かったです。
もう1つ重要なのはビーチバレーの基本的なプレー。それをより深く意識して体に覚え込ませないといけなかった。根気強くやるんだと言い聞かせましたね。
――6人制とは違って、2人の場合はより連携を密にしないといけないですね。
はい。やっていけると思えたのは2年目かな。
そこからは徐々にレベルアップしていきました。最初からできる選手もいると思うんですけど、その場合はペア選手のレベルの高さに後押しされている場合が多い。自分ができたと勘違いしちゃうと成長がないまま終わるケースが多いというのが正直なところです。
――新たな自分自身に出会えた?
より自分自身に向き合うことができて、やりやすい競技だと感じましたね。
僕はもともとすごく我が強いんで、インドアの頃から「自分はこういうことをやって成長していくんだ」という確固たる信念がありました。五輪出場という目標があるのなら、チームの約束ごとさえ守っていたら、プロセスは人それぞれでいい。協調性がないというわけじゃないんですけど、そういう考え方だったんです。
でも、チームっていうのはみんなが右向け右でやる傾向が強いですよね。当時のインドアは僕が好き勝手やって責任を取ればいいという環境じゃなかった。今になると理解できますが、しっくりこないところがあったのは事実です。
その点、ビーチバレーボールは2人でやる競技なんで、自分自身が全ての責任を背負わなければいけない。悪ければ自分のせいということになりますし、プロセスに対して責任もってやれる環境にあるのは確か。そこは僕にとっては合うんじゃないかなと思いますね。