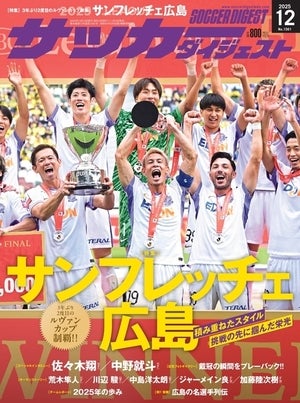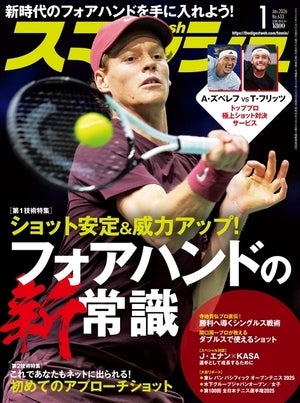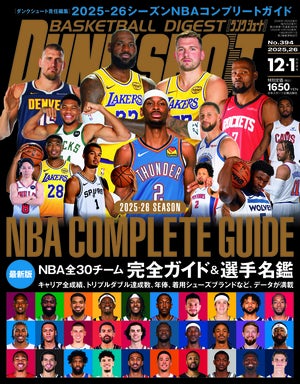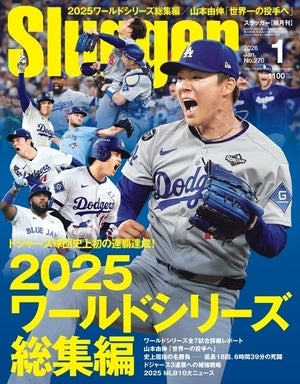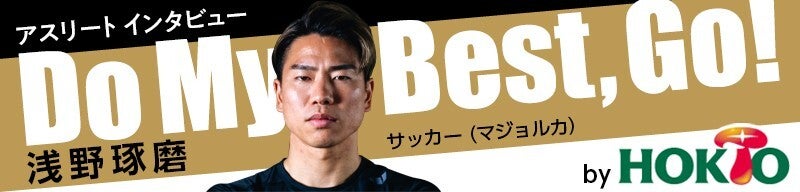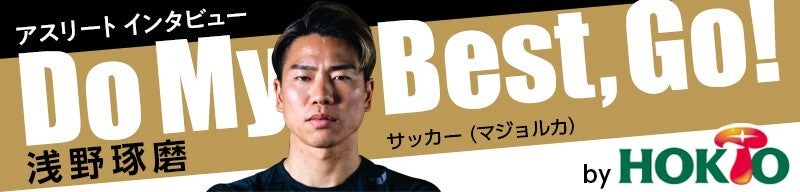イタリアが技術・戦術的にだけでなく精神的にもいかに追い詰められていたかが如実に現われたのが、30分にPKで先制を許した6分後の2失点目だ。GKの主将ドンナルンマがシュートを右手で弾き出してCKに逃れた後、ゴールから離れてチームメイトを叱責。プレーの展開から目を離して言い合いするイタリア守備陣の注意散漫を見逃さなかったキッカーのキミッヒは、ボールボーイに目配せしてボールを受け取ると素早くCKを蹴り、ゴール前で待っていたムシアラが無人のゴールに流し込んだ。
さらに前半終了間際の45分には、キミッヒのアシストをクラインディーンストがまたも頭で押し込んで3ー0。イタリアがここまで一方的にやり込められたのは、EURO2024のスペイン戦以来だろう。手も足も出ない、という表現がこれ以上ないほどぴったり当てはまる45分だった。
スパレッティ監督は後半、ビルドアップでミスを繰り返したCBガッティ、代表初先発の重圧もあってか、前線で縦パスをほとんど収められずポゼッション確立にほとんど寄与できなかったマルディーニを下げてポリターノとフラッテージを投入、ディ・ロレンツォをWBから右CBに下ろすと同時に、中盤を厚くしてビルドアップの出口を増やすという対応を取った。
この修正に加え、3点リードして2試合合計5ー1という大差を得たドイツが明らかにペースを落としてプレスの開始点を下げてきたことで、ようやく呼吸ができるようになったイタリアは、49分にハイプレスで相手のミスを誘い、そのこぼれ球を拾ったケーンが直接ねじ込んで1点を返す。
ここから試合はある程度拮抗した展開になり、69分にはイタリアが自陣からのビルドアップでドイツの中央を攻略、再びケーンが決めて3ー2(2試合合計5ー3)とする。さらに73分、右サイドのコンビネーションから抜け出したディ・ロレンツォをシュロッターベックが倒してPKの笛。これで流れは完全にイタリアの側に傾いたかに見えた。
ところがこの判定にVARが介入してPKは取り消しに。接触はなかったという指摘だったが、別の角度からのリプレイでは明らかな接触が確認でき、結果的には介入したVARの方が誤審だったことが、後になって判明する。もしこのPKが認められてイタリアが3ー3(2試合合計5ー4)まで迫っていれば、残り時間はまだ20分あっただけに、この後の試合はまったく別の展開になったかもしれない。
しかしVARの介入で覆った判定は動かない。イタリアはその後も押し気味に試合を進めるが明確な決定機を作り出すには至らず、90分を回ったところで得たPK(CKからの競り合いで相手がハンド)をラスパドーリが決めて3ー3とするも、そこまでだった。
後半の45分は互角かそれ以上に渡り合って3点を奪ったものの、それは前半の3失点で大勢が決し、ドイツがやや緊張を解いたのにつけ込んだ結果。スコアは3ー3だったものの、印象としてはまったく何もさせてもらえなかった前半の方が強く残った試合ではあった。プレッシャー下でのビルドアップ能力向上、ダイレクトアタックを含む「プランB」の開拓は今後の大きな課題だろう。
とはいえ、ネーションズリーグのリーグフェーズ6試合と準々決勝の2試合、計8試合を一貫して「インテルモデル」の3ー5ー2で戦ったことで、イタリアが明確なアイデンティティーを確立し、フランス、ドイツといった強豪ともそれなりに渡り合えるメドが立ったのは喜ばしいことだ。
戦力的に見れば、個のクオリティーによってワンプレーで決定的な違いを作り出せるワールドクラスを擁していないという点で、イングランド、ドイツ、スペイン、フランスといったトップレベルの強豪国との間に明らかな差があることは否定できない。
しかし、前線のレテギ、ケーン、中盤のバレッラ、トナーリ、そして攻撃でも重要な役割を果たすWBのカンビアーゾ、ディマルコ、そして最終ラインのバストーニ、カラフィオーリと、現時点でイタリアが擁する最も質の高い選手たちが、それぞれの持ち味を発揮できる適材適所に収まり、チームとしてのコレクティブな機能性を確立しつつあること、それが強豪国相手にも戦術的な優位性を発揮する可能性が見えたことは、ポジティブに捉えるべきだろう。進むべき道が定まっただけでなく、チームとしての伸びしろはまだまだ残されている。
ネーションズリーグ敗退で6月のファイナル4進出がなくなった代わりに、イタリアはグループI(ノルウェー、イスラエル、エストニア、モルドバ)に割り当てられたW杯予選がスタート。6月8日の初戦は、最も警戒すべき相手であるノルウェーとのアウェー戦だ。
アーリング・ハーランド、アレクサンデル・スルロットというツインタワーとの空中戦をどう制するか、司令塔マーティン・ウーデゴーをいかに封じるかが、14年のブラジル大会以来12年ぶり(!)のW杯出場に向けて、順調なスタートを切るうえで大きな課題になりそうだ。
文●片野道郎
【記事】“コントロール”を失わなかったインテルと、“軽率かつ重大な失態”のアタランタ。上位対決の分水嶺は「経験値の差」【現地発コラム】
【記事】ミランとインテルの「新サン・シーロ計画」紆余曲折を経て再始動! 一時は別々に建てる方針だったが…現スタジアムの隣接地に共同建設へ【現地発コラム】
さらに前半終了間際の45分には、キミッヒのアシストをクラインディーンストがまたも頭で押し込んで3ー0。イタリアがここまで一方的にやり込められたのは、EURO2024のスペイン戦以来だろう。手も足も出ない、という表現がこれ以上ないほどぴったり当てはまる45分だった。
スパレッティ監督は後半、ビルドアップでミスを繰り返したCBガッティ、代表初先発の重圧もあってか、前線で縦パスをほとんど収められずポゼッション確立にほとんど寄与できなかったマルディーニを下げてポリターノとフラッテージを投入、ディ・ロレンツォをWBから右CBに下ろすと同時に、中盤を厚くしてビルドアップの出口を増やすという対応を取った。
この修正に加え、3点リードして2試合合計5ー1という大差を得たドイツが明らかにペースを落としてプレスの開始点を下げてきたことで、ようやく呼吸ができるようになったイタリアは、49分にハイプレスで相手のミスを誘い、そのこぼれ球を拾ったケーンが直接ねじ込んで1点を返す。
ここから試合はある程度拮抗した展開になり、69分にはイタリアが自陣からのビルドアップでドイツの中央を攻略、再びケーンが決めて3ー2(2試合合計5ー3)とする。さらに73分、右サイドのコンビネーションから抜け出したディ・ロレンツォをシュロッターベックが倒してPKの笛。これで流れは完全にイタリアの側に傾いたかに見えた。
ところがこの判定にVARが介入してPKは取り消しに。接触はなかったという指摘だったが、別の角度からのリプレイでは明らかな接触が確認でき、結果的には介入したVARの方が誤審だったことが、後になって判明する。もしこのPKが認められてイタリアが3ー3(2試合合計5ー4)まで迫っていれば、残り時間はまだ20分あっただけに、この後の試合はまったく別の展開になったかもしれない。
しかしVARの介入で覆った判定は動かない。イタリアはその後も押し気味に試合を進めるが明確な決定機を作り出すには至らず、90分を回ったところで得たPK(CKからの競り合いで相手がハンド)をラスパドーリが決めて3ー3とするも、そこまでだった。
後半の45分は互角かそれ以上に渡り合って3点を奪ったものの、それは前半の3失点で大勢が決し、ドイツがやや緊張を解いたのにつけ込んだ結果。スコアは3ー3だったものの、印象としてはまったく何もさせてもらえなかった前半の方が強く残った試合ではあった。プレッシャー下でのビルドアップ能力向上、ダイレクトアタックを含む「プランB」の開拓は今後の大きな課題だろう。
とはいえ、ネーションズリーグのリーグフェーズ6試合と準々決勝の2試合、計8試合を一貫して「インテルモデル」の3ー5ー2で戦ったことで、イタリアが明確なアイデンティティーを確立し、フランス、ドイツといった強豪ともそれなりに渡り合えるメドが立ったのは喜ばしいことだ。
戦力的に見れば、個のクオリティーによってワンプレーで決定的な違いを作り出せるワールドクラスを擁していないという点で、イングランド、ドイツ、スペイン、フランスといったトップレベルの強豪国との間に明らかな差があることは否定できない。
しかし、前線のレテギ、ケーン、中盤のバレッラ、トナーリ、そして攻撃でも重要な役割を果たすWBのカンビアーゾ、ディマルコ、そして最終ラインのバストーニ、カラフィオーリと、現時点でイタリアが擁する最も質の高い選手たちが、それぞれの持ち味を発揮できる適材適所に収まり、チームとしてのコレクティブな機能性を確立しつつあること、それが強豪国相手にも戦術的な優位性を発揮する可能性が見えたことは、ポジティブに捉えるべきだろう。進むべき道が定まっただけでなく、チームとしての伸びしろはまだまだ残されている。
ネーションズリーグ敗退で6月のファイナル4進出がなくなった代わりに、イタリアはグループI(ノルウェー、イスラエル、エストニア、モルドバ)に割り当てられたW杯予選がスタート。6月8日の初戦は、最も警戒すべき相手であるノルウェーとのアウェー戦だ。
アーリング・ハーランド、アレクサンデル・スルロットというツインタワーとの空中戦をどう制するか、司令塔マーティン・ウーデゴーをいかに封じるかが、14年のブラジル大会以来12年ぶり(!)のW杯出場に向けて、順調なスタートを切るうえで大きな課題になりそうだ。
文●片野道郎
【記事】“コントロール”を失わなかったインテルと、“軽率かつ重大な失態”のアタランタ。上位対決の分水嶺は「経験値の差」【現地発コラム】
【記事】ミランとインテルの「新サン・シーロ計画」紆余曲折を経て再始動! 一時は別々に建てる方針だったが…現スタジアムの隣接地に共同建設へ【現地発コラム】
関連記事
- “コントロール”を失わなかったインテルと、“軽率かつ重大な失態”のアタランタ。上位対決の分水嶺は「経験値の差」【現地発コラム】
- ミランとインテルの「新サン・シーロ計画」紆余曲折を経て再始動! 一時は別々に建てる方針だったが…現スタジアムの隣接地に共同建設へ【現地発コラム】
- “三兎を追う”満身創痍のインテルは「今後2週間が重要な節目」スクデット争いは、セリエAに専念できるナポリが有利か【現地発コラム】
- “ベスト16をドブに捨てた”ミランのCL敗退、「戦力や戦術以上に、チームの結束やクラブとの信頼関係にかかわる組織論的な問題が――」【現地発コラム】
- 世界的観光地を本拠地とする“プロビンチャーレ”コモの野望――シティ、パリSGを上回る資産7.5兆円オーナーが目指す「サッカークラブの枠を大きく超えたビジネス」【現地発コラム】