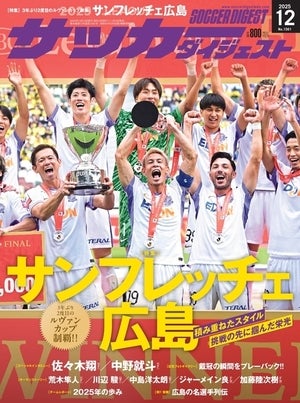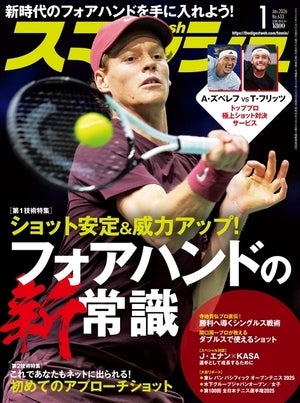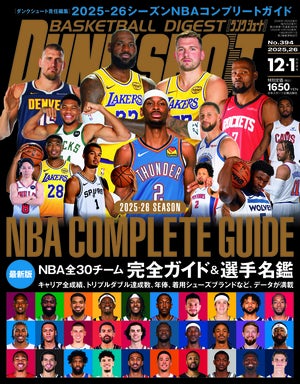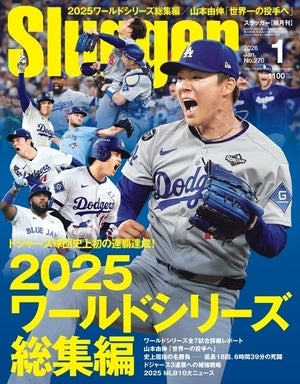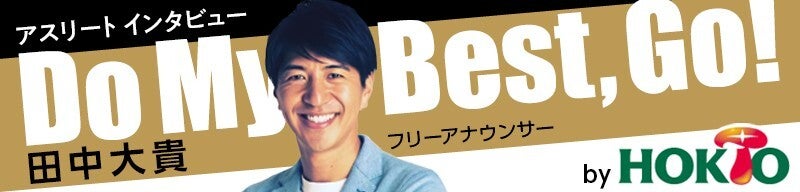一方のインテルは、バルセロナはもちろん他の2チーム(パリ・サンジェルマン、アーセナル)と比べても明らかに異質なチームだ。唯一3バック(3ー5ー2)の基本システムを採用しているだけでなく、ボール支配も地域の支配にも強いこだわりを持たず、相手との力関係(や戦術的なマッチング)に応じて柔軟に戦い方を変えることができる。セリエAではリーグトップの支配率(59.5%)を誇りながら、CLでは50.3%に留まっているのは象徴的だ。準々決勝のバイエルン戦でも、第1レグ45%、第2レグ40%と、明らかに相手にボールを持たせる戦い方を選んでいる。
攻撃のコンセプトも大きく異なっている。バルセロナ、パリSG、アーセナルはいずれも、ビルドアップ時に3ー2ー5や2ー3ー5といったバランスよく前線を広くカバーする「ポジショナルな」配置を取り、後方からショートパスを繋いで前進して、敵2ライン(MFとDF)間に位置するアタッカーにクリーンなボールを届けることを目的としてプレーしている。その過程でチーム全体を押し上げ、敵陣に進出して相手を「押し込む」こと、そのうえでドリブル突破やコンビネーションを駆使してファイナルサードを攻略することが狙いだ。
しかしインテルはむしろ、自陣でボールを動かすことで相手のプレスを誘引し、そこから攻撃を縦に加速して背後のスペースを衝くことをビルドアップの根幹に据えている。相手を「押し込む」のではなく「引き出す」ことで、ファイナルサードを一気に攻略する下地を整えるという発想である。
ボール保持にそれほどこだわらず、自陣にローブロックを敷いて相手を受け止めることを許容するのもそのため。一見すると「押し込まれて」いるように見える状況も、インテルにとっては「引き出して」あるいは「おびき出して」いるという側面も(部分的にはだが)あるわけだ。
そうして自陣でボールを奪ってからの展開は、自陣でボールを動かしながら縦への展開を窺っている状況と大きくは変わらない。相手のプレスを外して前を向いたところから、縦パスとポストプレー、その落としを受けてさらに縦パスやサイドチェンジ、といった形で足下ではなくスペースにボールをつないで一気に前進し、相手の背後を衝いて一気にフィニッシュを狙っていく。
攻撃のデータを見ると、インテルは4チーム中最低の数字しか記録していない。1試合平均得点(1.50)、ゴール期待値(1.72)、枠内シュート(3.83)はいずれも4チーム中4位。しかし守備のデータは、失点(0.42)、被ゴール期待値(0.72)が1位、被枠内シュート(3.67)もアーセナルに次いで少ない。12試合中クリーンシートが8試合という数字は傑出したものだ。
ボールを保持して攻めることもできるが、相手に持たせて受けに回っても試合のコントロールを失うことなく戦えるのは、他にはない強みだ。4チームの中ではアーセナルもそうした側面を持っているが、リーグフェーズでそのアーセナルに63%の支配率を許しつつも1ー0で下しているように、守備をベースにした試合運びではインテルが一枚上手である。
攻撃力という点から見れば、インテルはバルセロナに遠く及ばないことは明らかだ。しかし戦術スタイルという観点から見ると、バルセロナに対する「相性」はまったく悪くない。バルセロナは、相手を押し込んだ後のプレスの圧力、奪回の速さにおいては傑出しているが、一旦そのプレスを外されてハイラインの裏を衝かれた時には脆さを露呈するところがある。1試合平均失点1.42、被ゴール期待値1.47(実際の失点よりも高い)、被枠内シュート4.08という数字を見ても、ボールを持っていない時の不安定さは明らか。インテルにとってはまさにそこが格好の狙い目になるはずだ。
前述したリーグフェーズのアーセナル戦、準々決勝のバイエルン戦2試合、さらには2年前にマンチェスター・シティをひどく苦しめたCL決勝などを見てもわかるように、インテルは「ボールと地域を支配」して戦うチームを困難に陥れる確かな術を持っている。明らかに劣勢に立たされるであろうにもかかわらず、「15年前の再現」をサポーターやマスコミが夢見る理由もまたそこにある。
文●片野道郎
【記事】モッタ解任→トゥードル招聘、2億ユーロのプロジェクトに失敗したユベントス。夏の監督選びこそ「最後になるべき“再スタート”の始まり」【現地発コラム】
【記事】“コントロール”を失わなかったインテルと、“軽率かつ重大な失態”のアタランタ。上位対決の分水嶺は「経験値の差」【現地発コラム】
攻撃のコンセプトも大きく異なっている。バルセロナ、パリSG、アーセナルはいずれも、ビルドアップ時に3ー2ー5や2ー3ー5といったバランスよく前線を広くカバーする「ポジショナルな」配置を取り、後方からショートパスを繋いで前進して、敵2ライン(MFとDF)間に位置するアタッカーにクリーンなボールを届けることを目的としてプレーしている。その過程でチーム全体を押し上げ、敵陣に進出して相手を「押し込む」こと、そのうえでドリブル突破やコンビネーションを駆使してファイナルサードを攻略することが狙いだ。
しかしインテルはむしろ、自陣でボールを動かすことで相手のプレスを誘引し、そこから攻撃を縦に加速して背後のスペースを衝くことをビルドアップの根幹に据えている。相手を「押し込む」のではなく「引き出す」ことで、ファイナルサードを一気に攻略する下地を整えるという発想である。
ボール保持にそれほどこだわらず、自陣にローブロックを敷いて相手を受け止めることを許容するのもそのため。一見すると「押し込まれて」いるように見える状況も、インテルにとっては「引き出して」あるいは「おびき出して」いるという側面も(部分的にはだが)あるわけだ。
そうして自陣でボールを奪ってからの展開は、自陣でボールを動かしながら縦への展開を窺っている状況と大きくは変わらない。相手のプレスを外して前を向いたところから、縦パスとポストプレー、その落としを受けてさらに縦パスやサイドチェンジ、といった形で足下ではなくスペースにボールをつないで一気に前進し、相手の背後を衝いて一気にフィニッシュを狙っていく。
攻撃のデータを見ると、インテルは4チーム中最低の数字しか記録していない。1試合平均得点(1.50)、ゴール期待値(1.72)、枠内シュート(3.83)はいずれも4チーム中4位。しかし守備のデータは、失点(0.42)、被ゴール期待値(0.72)が1位、被枠内シュート(3.67)もアーセナルに次いで少ない。12試合中クリーンシートが8試合という数字は傑出したものだ。
ボールを保持して攻めることもできるが、相手に持たせて受けに回っても試合のコントロールを失うことなく戦えるのは、他にはない強みだ。4チームの中ではアーセナルもそうした側面を持っているが、リーグフェーズでそのアーセナルに63%の支配率を許しつつも1ー0で下しているように、守備をベースにした試合運びではインテルが一枚上手である。
攻撃力という点から見れば、インテルはバルセロナに遠く及ばないことは明らかだ。しかし戦術スタイルという観点から見ると、バルセロナに対する「相性」はまったく悪くない。バルセロナは、相手を押し込んだ後のプレスの圧力、奪回の速さにおいては傑出しているが、一旦そのプレスを外されてハイラインの裏を衝かれた時には脆さを露呈するところがある。1試合平均失点1.42、被ゴール期待値1.47(実際の失点よりも高い)、被枠内シュート4.08という数字を見ても、ボールを持っていない時の不安定さは明らか。インテルにとってはまさにそこが格好の狙い目になるはずだ。
前述したリーグフェーズのアーセナル戦、準々決勝のバイエルン戦2試合、さらには2年前にマンチェスター・シティをひどく苦しめたCL決勝などを見てもわかるように、インテルは「ボールと地域を支配」して戦うチームを困難に陥れる確かな術を持っている。明らかに劣勢に立たされるであろうにもかかわらず、「15年前の再現」をサポーターやマスコミが夢見る理由もまたそこにある。
文●片野道郎
【記事】モッタ解任→トゥードル招聘、2億ユーロのプロジェクトに失敗したユベントス。夏の監督選びこそ「最後になるべき“再スタート”の始まり」【現地発コラム】
【記事】“コントロール”を失わなかったインテルと、“軽率かつ重大な失態”のアタランタ。上位対決の分水嶺は「経験値の差」【現地発コラム】
関連記事
- モッタ解任→トゥードル招聘、2億ユーロのプロジェクトに失敗したユベントス。夏の監督選びこそ「最後になるべき“再スタート”の始まり」【現地発コラム】
- “コントロール”を失わなかったインテルと、“軽率かつ重大な失態”のアタランタ。上位対決の分水嶺は「経験値の差」【現地発コラム】
- ミランとインテルの「新サン・シーロ計画」紆余曲折を経て再始動! 一時は別々に建てる方針だったが…現スタジアムの隣接地に共同建設へ【現地発コラム】
- “三兎を追う”満身創痍のインテルは「今後2週間が重要な節目」スクデット争いは、セリエAに専念できるナポリが有利か【現地発コラム】
- “ベスト16をドブに捨てた”ミランのCL敗退、「戦力や戦術以上に、チームの結束やクラブとの信頼関係にかかわる組織論的な問題が――」【現地発コラム】