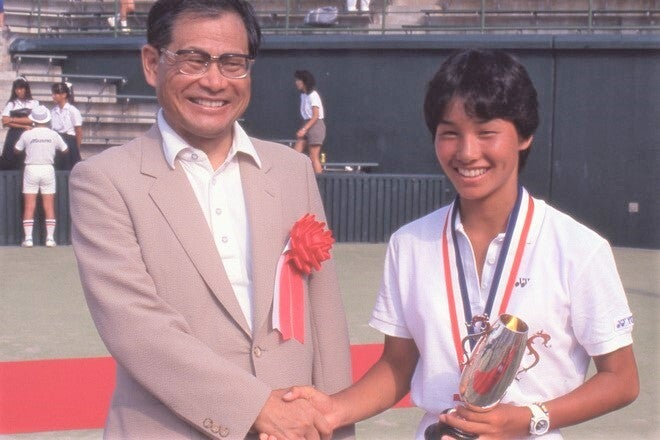かくして「たまたま」通いはじめたテニスクラブには、オーストラリアテニスに感銘を受けた竹内穣治という名伯楽が居て、伊達の一歳年長には、竹内が育てた“天才少女”の木戸脇真也が居た。なお穣治氏の息子で当時既にプロとして活動していたのが、竹内映二。後に伊達公子のコーチをつとめ、現在も日比野菜緒に帯同する日本屈指のツアーコーチである。
そのような名門テニスクラブにおける伊達の位置づけは、本人曰く「劣等生」だった。
「四ノ宮は山を削って作ったクラブで、山の上に2面、下に一面、コートがあるんです。上に行くほど、強い選手。わたしも強化選手に入っていたんですが、なかなか上にいけない。たまに上のコートに呼ばれるけれど、またすぐ下に落とされる。木戸脇さんのような強い子は、常に上。わたしは基本、下のコートでした」
山の斜面に施工されたコートの高度が、選手のヒエラルキーをも可視化する、ある意味での実力主義。指導方針は「選手の自主性に任せる」というテニスクラブにおいて、下のコートは放任状態だったという。
ただ、当時を回想する伊達の言葉が結ぶ像は、細い手足をしならせて野山を駆け、自由を謳歌する、明るく活発な「自然児」だ。
「ときどき田んぼに遊びに行ったり、スーパーに行って家では食べられないお菓子を買ったり。下のコートで総当たり戦などをやっている時は、コーチもあまり見てなかったと思います」
とはいえ「放任」状態においても、一本芯の通った指導指針はある。
「とにかく練習は、ネットプレーが中心。木戸脇さんや(竹内)映二さんがいたこともあり、譲治先生の視線は常に世界を向いていたと思います。『ネットプレーをやらなくてはダメだ、世界に行くにはそれが必要だ』という方針でした」
もっともそのネットプレーにしても、当時の彼女に「強くなるにはこれが必要だ、との思いは、一切なかった」という。無自覚に磨いた武器の効力に彼女自身が気付くのは、さらに数年後のことである。
生まれ育った環境や年齢が近いがために、ともに歩んだ友人やライバルも、やがては人生の「分かれ道」へと至るのは世の摂理だろう。
「京都の4人組」にも、そんな時が訪れた。
それが、高校進学。
京都で常に上位を占めた少女たちの下には、兵庫県神戸のスポーツ名門校、夙川高校から推薦入学の声が掛かった。もちろん、伊達もその一人。だが彼女は、その道を選ばなかった。
「わたしは寮生活に憧れていたので、寮がある高校が良かった。それに京都のみんなが夙川に行くので、またずっと一緒にやるのも嫌だったし……」
劣等生だったので――と彼女は、笑って加える。
家を出て、京都を出て、いつもの顔ぶれから抜け出して……そうして新たな環境を求めた彼女は、兵庫県尼崎市の園田学園への進学を望んだ。
とはいえ、同校から推薦をもらえたわけではない。そこで竹内譲治の助力を求めるが、伊達の即プロ転向を望んでいた竹内には、「そんなところに行くか!」とけんもほろろに断られた。
「困ったな」と途方に暮れた彼女に、手を差し伸べてくれたのは、最初に通っていたテニスクラブのオーナーである。そこで連れたって園田学園に足を運ぶが、高校テニス部の監督である光國彰氏は、伊達のことを知らなかった様子。ただ、伊達を知っていた大学の監督が「オッケーと言ってくれた」ために、なんとか推薦入学へとこぎつけた。
「そこも大きな転機でしたね。流されて夙川に行っていたら、今の自分は無かったですね、たぶん」
彼女がポツリと、そう言った。
そのような名門テニスクラブにおける伊達の位置づけは、本人曰く「劣等生」だった。
「四ノ宮は山を削って作ったクラブで、山の上に2面、下に一面、コートがあるんです。上に行くほど、強い選手。わたしも強化選手に入っていたんですが、なかなか上にいけない。たまに上のコートに呼ばれるけれど、またすぐ下に落とされる。木戸脇さんのような強い子は、常に上。わたしは基本、下のコートでした」
山の斜面に施工されたコートの高度が、選手のヒエラルキーをも可視化する、ある意味での実力主義。指導方針は「選手の自主性に任せる」というテニスクラブにおいて、下のコートは放任状態だったという。
ただ、当時を回想する伊達の言葉が結ぶ像は、細い手足をしならせて野山を駆け、自由を謳歌する、明るく活発な「自然児」だ。
「ときどき田んぼに遊びに行ったり、スーパーに行って家では食べられないお菓子を買ったり。下のコートで総当たり戦などをやっている時は、コーチもあまり見てなかったと思います」
とはいえ「放任」状態においても、一本芯の通った指導指針はある。
「とにかく練習は、ネットプレーが中心。木戸脇さんや(竹内)映二さんがいたこともあり、譲治先生の視線は常に世界を向いていたと思います。『ネットプレーをやらなくてはダメだ、世界に行くにはそれが必要だ』という方針でした」
もっともそのネットプレーにしても、当時の彼女に「強くなるにはこれが必要だ、との思いは、一切なかった」という。無自覚に磨いた武器の効力に彼女自身が気付くのは、さらに数年後のことである。
生まれ育った環境や年齢が近いがために、ともに歩んだ友人やライバルも、やがては人生の「分かれ道」へと至るのは世の摂理だろう。
「京都の4人組」にも、そんな時が訪れた。
それが、高校進学。
京都で常に上位を占めた少女たちの下には、兵庫県神戸のスポーツ名門校、夙川高校から推薦入学の声が掛かった。もちろん、伊達もその一人。だが彼女は、その道を選ばなかった。
「わたしは寮生活に憧れていたので、寮がある高校が良かった。それに京都のみんなが夙川に行くので、またずっと一緒にやるのも嫌だったし……」
劣等生だったので――と彼女は、笑って加える。
家を出て、京都を出て、いつもの顔ぶれから抜け出して……そうして新たな環境を求めた彼女は、兵庫県尼崎市の園田学園への進学を望んだ。
とはいえ、同校から推薦をもらえたわけではない。そこで竹内譲治の助力を求めるが、伊達の即プロ転向を望んでいた竹内には、「そんなところに行くか!」とけんもほろろに断られた。
「困ったな」と途方に暮れた彼女に、手を差し伸べてくれたのは、最初に通っていたテニスクラブのオーナーである。そこで連れたって園田学園に足を運ぶが、高校テニス部の監督である光國彰氏は、伊達のことを知らなかった様子。ただ、伊達を知っていた大学の監督が「オッケーと言ってくれた」ために、なんとか推薦入学へとこぎつけた。
「そこも大きな転機でしたね。流されて夙川に行っていたら、今の自分は無かったですね、たぶん」
彼女がポツリと、そう言った。