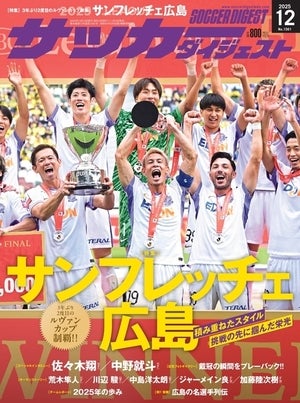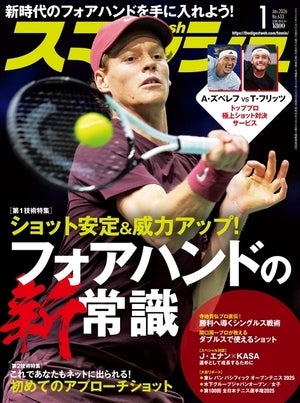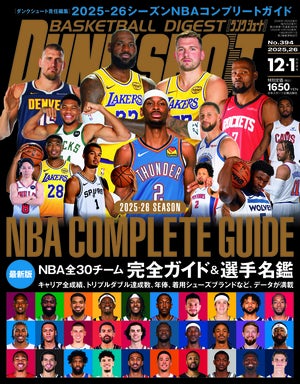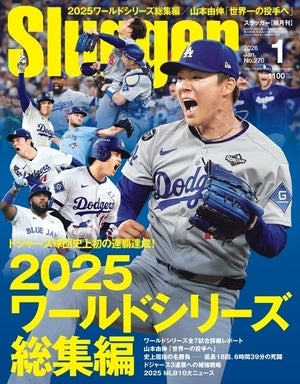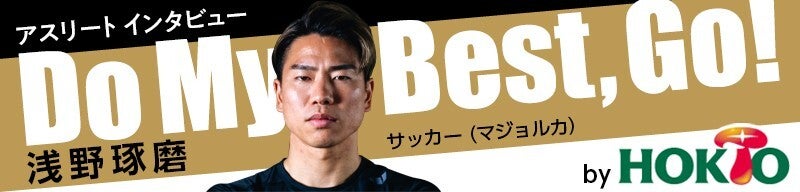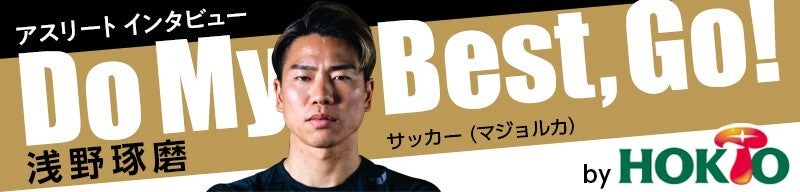ウィーバーが通算退場回数97回が、今もア・リーグ記録として残る猛者で、ワールドシリーズでもストライク/ボール判定に抗議して退場になっている(これは史上3人しかいない)。ルチアーノはウィーバーに対して、マイナー時代に4試合連続退場を宣告。メジャーになっても通算8回も退場させた。
先に書いた『アンパイアの逆襲』の中でも、ルチアーノは嫌いだった監督や選手のベスト10として、1位から9位までにウィーバーを挙げている(10位は「ウィーバーの指示に忠実だった」という理由で、元オリオールズの外野手で66年には三冠王となったフランク・ロビンソンが選ばれている)。だが、ウィーバーはルチアーノの審判としての能力は高く評価していたらしく、両者は天敵ではなく好敵手と言うべきかもしれない。
日本のプロ野球にも、かつて“名物審判”がいた。
選手として34年に結成された大日本東京野球倶楽部(後の読売ジャイアンツ)にも参加し、その後はパ・リーグの名審判として名を馳せた二出川延明氏が有名だ。
彼は「俺がルールブックだ」という名言でも知られる。59年の大毎オリオンズ(現ロッテ)対西鉄ライオンズ(現西武)戦でのことだ。大毎の走者が二塁に滑り込んだのと送球が同時で、セーフの判定。これに納得がいかなかった西鉄の三原修監督が、審判控え室にいた二出川審判長にも抗議を繰り返し、挙句に、「ルールブックを見せろ」とまで言った。その時、二出川審判長が言い放ったのがこのセリフだった。
しかし、ルールブックには「同時はセーフ」という言葉はない。どのような場合に打者走者や走者がアウトになるか、という記述だけでも公認野球規則では何と12ページも割いているので、よく読まないと分からないが、「走者が次の塁に触れる前に、その塁に(野手)が触球した場合」はアウトと書かれている。従って、論理的には「同時はセーフ」と解釈できるのだ。この複雑な文章の解釈を省略して「俺がルールブック」と言い放った二出川氏はさすがと言える。
二出川氏は他にも、アウト/セーフの判定を間違った証拠として写真を見せた新聞記者に対し、平然と「写真が間違っている」と言い放ったとか、誰が見てもド真ん中の直球を「ボール!」とコールし、捕手と投手が抗議すると「気合いが入っていないからボールだ!」と反論したとか、プロ野球史上初の退場を宣告したとか、さまざまな逸話がある。日本プロ野球史上最も名を馳せた“名物審判”と言える。
しかし、ロボット審判やビデオ判定の導入で、もはやMLBではルチアーノや二出川氏のような審判は消え去るに違いない。これはやはり寂しいことと思うのは、小生が歳を取った証拠なのだろうか? そういえば最近は、審判と監督の罵り合いも少なくなり、選手同士の乱闘もほとんど見られなくなった。
そのような風潮は、あるいはベールボールが「大人の球戯」を脱し、完全にスポーツとして成熟した証拠と言えるのかもしれない。
文●玉木正之
【著者プロフィール】
たまき・まさゆき。1952年生まれ。東京大学教養学部中退。在学中から東京新聞、雑誌『GORO』『平凡パンチ』などで執筆を開始。日本で初めてスポーツライターを名乗る。現在の肩書きは、スポーツ文化評論家・音楽評論家。日本経済新聞や雑誌『ZAITEN』『スポーツゴジラ』等で執筆活動を続け、BSフジ『プライムニュース』等でコメンテーターとして出演。主な書籍は『スポーツは何か』(講談社現代新書)『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)など。訳書にR・ホワイティング『和を以て日本となす』(角川文庫)ほか。
先に書いた『アンパイアの逆襲』の中でも、ルチアーノは嫌いだった監督や選手のベスト10として、1位から9位までにウィーバーを挙げている(10位は「ウィーバーの指示に忠実だった」という理由で、元オリオールズの外野手で66年には三冠王となったフランク・ロビンソンが選ばれている)。だが、ウィーバーはルチアーノの審判としての能力は高く評価していたらしく、両者は天敵ではなく好敵手と言うべきかもしれない。
日本のプロ野球にも、かつて“名物審判”がいた。
選手として34年に結成された大日本東京野球倶楽部(後の読売ジャイアンツ)にも参加し、その後はパ・リーグの名審判として名を馳せた二出川延明氏が有名だ。
彼は「俺がルールブックだ」という名言でも知られる。59年の大毎オリオンズ(現ロッテ)対西鉄ライオンズ(現西武)戦でのことだ。大毎の走者が二塁に滑り込んだのと送球が同時で、セーフの判定。これに納得がいかなかった西鉄の三原修監督が、審判控え室にいた二出川審判長にも抗議を繰り返し、挙句に、「ルールブックを見せろ」とまで言った。その時、二出川審判長が言い放ったのがこのセリフだった。
しかし、ルールブックには「同時はセーフ」という言葉はない。どのような場合に打者走者や走者がアウトになるか、という記述だけでも公認野球規則では何と12ページも割いているので、よく読まないと分からないが、「走者が次の塁に触れる前に、その塁に(野手)が触球した場合」はアウトと書かれている。従って、論理的には「同時はセーフ」と解釈できるのだ。この複雑な文章の解釈を省略して「俺がルールブック」と言い放った二出川氏はさすがと言える。
二出川氏は他にも、アウト/セーフの判定を間違った証拠として写真を見せた新聞記者に対し、平然と「写真が間違っている」と言い放ったとか、誰が見てもド真ん中の直球を「ボール!」とコールし、捕手と投手が抗議すると「気合いが入っていないからボールだ!」と反論したとか、プロ野球史上初の退場を宣告したとか、さまざまな逸話がある。日本プロ野球史上最も名を馳せた“名物審判”と言える。
しかし、ロボット審判やビデオ判定の導入で、もはやMLBではルチアーノや二出川氏のような審判は消え去るに違いない。これはやはり寂しいことと思うのは、小生が歳を取った証拠なのだろうか? そういえば最近は、審判と監督の罵り合いも少なくなり、選手同士の乱闘もほとんど見られなくなった。
そのような風潮は、あるいはベールボールが「大人の球戯」を脱し、完全にスポーツとして成熟した証拠と言えるのかもしれない。
文●玉木正之
【著者プロフィール】
たまき・まさゆき。1952年生まれ。東京大学教養学部中退。在学中から東京新聞、雑誌『GORO』『平凡パンチ』などで執筆を開始。日本で初めてスポーツライターを名乗る。現在の肩書きは、スポーツ文化評論家・音楽評論家。日本経済新聞や雑誌『ZAITEN』『スポーツゴジラ』等で執筆活動を続け、BSフジ『プライムニュース』等でコメンテーターとして出演。主な書籍は『スポーツは何か』(講談社現代新書)『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)など。訳書にR・ホワイティング『和を以て日本となす』(角川文庫)ほか。
関連記事
- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第18回】野村克也に稲尾和久、トム・シーバーまで...半世紀に及ぶスポーツライター歴で学んだ「一流選手から真理を聞き出す極意」<SLUGGER>
- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第17回】名物オーナーの奇抜なアイデアだったDH制度が球界のスタンダードになるまで<SLUGGER>
- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第16回】『ドカベン』も『野球狂の詩』も『スポーツマン金太郎』も読んでいたけれど…『巨人の星』だけは好きになれなかった理由<SLUGGER>
- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第15回】「それを作れば、彼らがやってくる」――アメリカ最高の野球映画『フィールド・オブ・ドリームス』の素晴らしさと“聖地”での思い出<SLUGGER>
- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第14回】令和のファンにとっては「よく知らない人」なのか…日本のプロ野球を創り上げた長嶋茂雄を永遠に語り継ごう<SLUGGER>