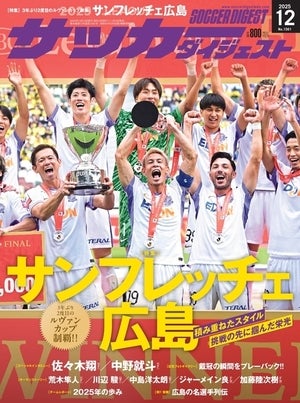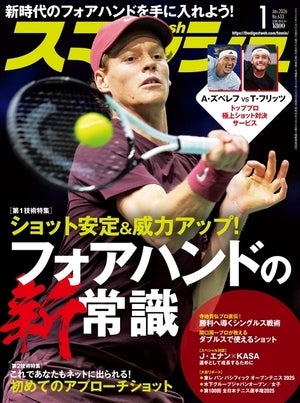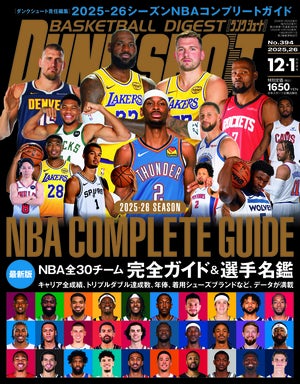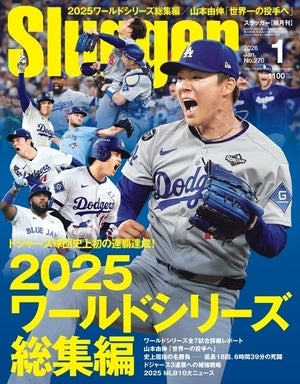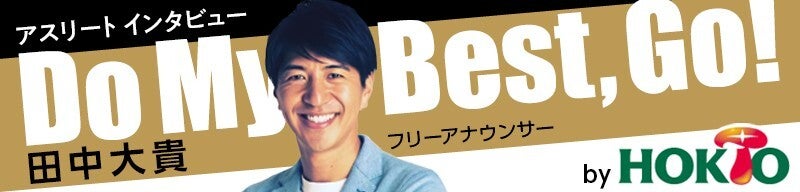日本がブラジルを史上初めて破る大金星を挙げたこの代表ウィーク、ヨーロッパで行なわれたワールドカップ欧州予選では、イタリアがエストニアに3-1、イスラエルに3-0で勝利を収め、グループ2位以上を確定させた。
ただ、仮に残り2試合に勝って1位のノルウェーと勝点で並んだとしても、現時点で16もの差がある得失点差を逆転することは非現実的。事実上、直接W杯に出場できる1位の座はノルウェーのものであり、2位のイタリアは3月に行なわれるプレーオフ(準決勝と決勝それぞれ一発勝負)に回ることになる。
6月にそのノルウェーに敗れて解任されたルチャーノ・スパレッティの後を受け、代表監督の座に就いたジェンナーロ・ガットゥーゾにとっては、これが二度目の代表ウィーク。今回の2試合の目標は、勝点6を確保してプレーオフ進出を確実にすることはもちろん、前回打ち出したマテオ・レテギ、モイゼ・ケーンの2トップに基盤を置くチームの構造を確立し、プレーオフ、そしてその先にあるW杯に向けた体制を固めることにあった。
10月11日にアウェーのタリンで行なわれたエストニア戦のスタメンは以下の通り。
システム:4-4-2
GK:ドンナルンマ
DF:ディ・ロレンツォ、バストーニ、カラフィオーリ、ディマルコ
MF:オルソリーニ、バレッラ、トナーリ、ラスパドーリ
FW:レテギ、ケーン
9月の試合で左右のウイングに入ったマッテオ・ポリターノ、マッティア・ザッカーニがいずれも故障で招集外となったため、右にリッカルド・オルソリーニ、左にジャコモ・ラスパドーリが起用された。それ以外の9人はガットゥーゾ体制のレギュラーと目される顔ぶれだ。
9月の同じエストニア戦(5-0で勝利)で見せた、ビルドアップ時に左SBのフェデリコ・ディマルコが速いタイミングで前線まで進出し、左WGラスパドーリがやや内に絞ることで形成される3-2-5の配置で攻撃を組み立てるメカニズムは、この試合でも立ち上がりから効果的に機能した。開始3分にラスパドーリがシュートを放った最初の決定機、その1分後に決まったケーンの先制ゴールはいずれも、右から組み立てて左にサイドを変え、そこからエリア内に斜めのパスを差し込む展開から生まれている。
残念だったのは、1-0とリードしてから間もなくケーンが右足首を傷め、15分に交代を強いられたこと。これによって、レテギとの2トップの連携を高め、チーム全体とプレーの感覚を共有する数少ない機会が失われてしまった。
ともに優れた得点感覚を持つだけでなく、前線中央で基準点となって縦パスを収めるレテギ、裏のスペースをアタックして最終ラインを押し下げるケーンと、異なる持ち味を持つ2人が形成する2トップは、「ガットゥーゾのイタリア」にとって最も重要な武器であると同時に、アイデンティティーの根幹をなす要素でもある。
交代で入ったFWフランチェスコ・ピオ・エスポージトは、現在インテルで急速に頭角を現わしつつある20歳の超有望株。2ライン(MFとDF)間に下がって縦パスを収める仕事を非常によくこなし、プレッシングでも献身的な働きを見せただけでなく、74分にはダメ押しとなる3点目のゴールも決めるなど、期待を上回る活躍を見せた。
ただ、タイプ的にはケーンよりもむしろレテギに近い純粋な基準点型センターフォワードで、レテギと組むと役割がややかぶる一方、裏のスペースアタックやカウンターといったオープンスペースを使う攻撃の切れ味が鈍るという側面もある。かつてマリオ・バロテッリが一時的にまばゆい輝きを見せて以来、10年以上にわたってCFの人材不足に悩まされてきたイタリアにとって、レテギ、ケーンに続く大型ストライカーの台頭は、望外の喜びではあるのだが。
試合は、地力に勝るイタリアが押し込む展開のまま進み、30分にレテギがPKを失敗したものの、38分にはやはり左サイドから攻め込んだ後、ディマルコのクロスがクリアされたボールをファーポスト際で拾ったオルソリーニのアシストをレテギが決めて2-0。
後半に入り、エストニアがそれまでの4バックから5バックにシステムを変更したことで、やや攻めあぐむ流れになったが、前述の通りピオ・エスポージトが3点目をゲット。その直後に、ジャンルイジ・ドンナルンマがクロスをキャッチし損ねて敵FWに詰められ1点を献上するアクシデントがあったものの、イタリアが順当な勝利を収めた。
ただ、仮に残り2試合に勝って1位のノルウェーと勝点で並んだとしても、現時点で16もの差がある得失点差を逆転することは非現実的。事実上、直接W杯に出場できる1位の座はノルウェーのものであり、2位のイタリアは3月に行なわれるプレーオフ(準決勝と決勝それぞれ一発勝負)に回ることになる。
6月にそのノルウェーに敗れて解任されたルチャーノ・スパレッティの後を受け、代表監督の座に就いたジェンナーロ・ガットゥーゾにとっては、これが二度目の代表ウィーク。今回の2試合の目標は、勝点6を確保してプレーオフ進出を確実にすることはもちろん、前回打ち出したマテオ・レテギ、モイゼ・ケーンの2トップに基盤を置くチームの構造を確立し、プレーオフ、そしてその先にあるW杯に向けた体制を固めることにあった。
10月11日にアウェーのタリンで行なわれたエストニア戦のスタメンは以下の通り。
システム:4-4-2
GK:ドンナルンマ
DF:ディ・ロレンツォ、バストーニ、カラフィオーリ、ディマルコ
MF:オルソリーニ、バレッラ、トナーリ、ラスパドーリ
FW:レテギ、ケーン
9月の試合で左右のウイングに入ったマッテオ・ポリターノ、マッティア・ザッカーニがいずれも故障で招集外となったため、右にリッカルド・オルソリーニ、左にジャコモ・ラスパドーリが起用された。それ以外の9人はガットゥーゾ体制のレギュラーと目される顔ぶれだ。
9月の同じエストニア戦(5-0で勝利)で見せた、ビルドアップ時に左SBのフェデリコ・ディマルコが速いタイミングで前線まで進出し、左WGラスパドーリがやや内に絞ることで形成される3-2-5の配置で攻撃を組み立てるメカニズムは、この試合でも立ち上がりから効果的に機能した。開始3分にラスパドーリがシュートを放った最初の決定機、その1分後に決まったケーンの先制ゴールはいずれも、右から組み立てて左にサイドを変え、そこからエリア内に斜めのパスを差し込む展開から生まれている。
残念だったのは、1-0とリードしてから間もなくケーンが右足首を傷め、15分に交代を強いられたこと。これによって、レテギとの2トップの連携を高め、チーム全体とプレーの感覚を共有する数少ない機会が失われてしまった。
ともに優れた得点感覚を持つだけでなく、前線中央で基準点となって縦パスを収めるレテギ、裏のスペースをアタックして最終ラインを押し下げるケーンと、異なる持ち味を持つ2人が形成する2トップは、「ガットゥーゾのイタリア」にとって最も重要な武器であると同時に、アイデンティティーの根幹をなす要素でもある。
交代で入ったFWフランチェスコ・ピオ・エスポージトは、現在インテルで急速に頭角を現わしつつある20歳の超有望株。2ライン(MFとDF)間に下がって縦パスを収める仕事を非常によくこなし、プレッシングでも献身的な働きを見せただけでなく、74分にはダメ押しとなる3点目のゴールも決めるなど、期待を上回る活躍を見せた。
ただ、タイプ的にはケーンよりもむしろレテギに近い純粋な基準点型センターフォワードで、レテギと組むと役割がややかぶる一方、裏のスペースアタックやカウンターといったオープンスペースを使う攻撃の切れ味が鈍るという側面もある。かつてマリオ・バロテッリが一時的にまばゆい輝きを見せて以来、10年以上にわたってCFの人材不足に悩まされてきたイタリアにとって、レテギ、ケーンに続く大型ストライカーの台頭は、望外の喜びではあるのだが。
試合は、地力に勝るイタリアが押し込む展開のまま進み、30分にレテギがPKを失敗したものの、38分にはやはり左サイドから攻め込んだ後、ディマルコのクロスがクリアされたボールをファーポスト際で拾ったオルソリーニのアシストをレテギが決めて2-0。
後半に入り、エストニアがそれまでの4バックから5バックにシステムを変更したことで、やや攻めあぐむ流れになったが、前述の通りピオ・エスポージトが3点目をゲット。その直後に、ジャンルイジ・ドンナルンマがクロスをキャッチし損ねて敵FWに詰められ1点を献上するアクシデントがあったものの、イタリアが順当な勝利を収めた。