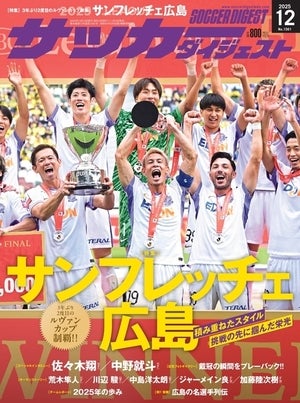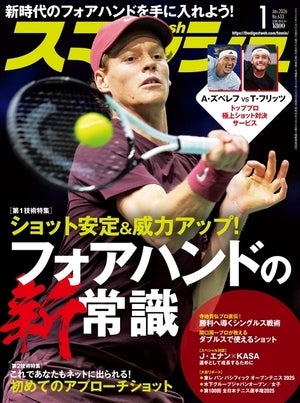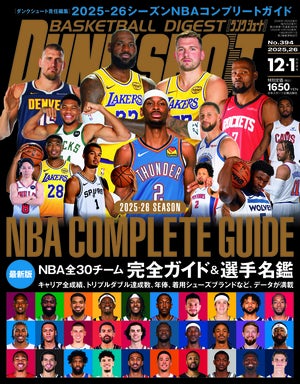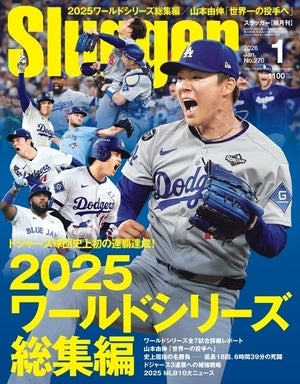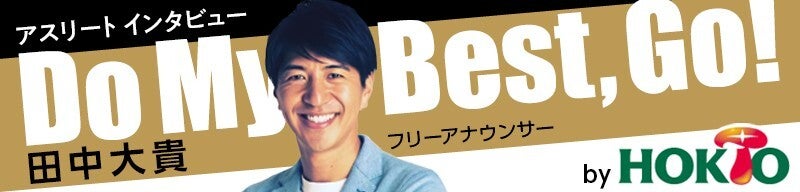イーゴル・トゥドル監督の下で陣容を少なからず入れ替え、新たなスタートを切ったユベントスは、3勝3分(勝点12)で首位から3ポイント差の5位。開幕3連勝の後はチャンピオンズリーグ2試合を含め5連続ドローとやや煮え切らない感はあるが、以下で見る前線の構成をはじめ、チームがまだ構築途上で固まっていない状況の中、インテル、アタランタ、ミランという上位陣と対戦してこの結果、この順位は決して悪くない。
ボール支配率(58.6%)、フィールドティルト(61.3%)はいずれもリーグ4位で、強敵相手の試合が多かったにもかかわらず、主導権を握って試合を進める力があることを示している。ただ、敵陣まではスムーズに前進できても、ラスト30m攻略に関しては課題を残しているように見える。
象徴的なのは、ファイナルサードへのパス本数(1試合平均34.8本)ではリーグ4位にもかかわらず、ペナルティーエリアへのパス本数(同7.8本)はトップ5の中で最も少ない7位に留まっていること。これはパスだけでなくキャリー(ドリブルでの持ち上がり)についても同じで、ファイナルサードへの侵入数(同19.2回)はリーグ1位だが、ペナルティーエリアへの侵入数(同3.83回)はリーグ13位。押し込みながらも攻め切れない課題がはっきりと浮かび上がってくる。
シュート数(1試合平均16.0本)、枠内シュート数(同5.33本)はいずれもリーグ3位と、決して悪くないように見える。しかし、そこから生み出されたゴール期待値(同1.21)はリーグ9位。決まる確率の低い強引なシュート、遠い距離からのシュートが多く、攻撃の量に質が伴っていないことは明らかだ。
今シーズンのユベントスは、契約最終年を迎えたドゥシャン・ヴラホビッチを売却し、昨季パリ・サンジェルマンからレンタルしていたランダル・コロ・ムアニを買い取って攻撃の中心に据える構想で移籍マーケットに臨みながら、この2つのオペレーションのどちらも完遂できず、シーズン開幕後も前線の陣容が固まらない困難に直面した。結果的には、リールとの契約満了でフリーになったジョナサン・デイビッドに加え、純粋なセンターフォワードではないロイス・オペンダを獲得。ヴラホビッチは残留という形に落ち着いた。
ここまでのところFW陣で最も好調に見えるのは、CLを含めて8試合で4得点をあげているそのヴラホビッチ。しかし、契約満了前の1月に移籍する可能性も残っているためかトゥドル監督はヴラホビッチを中核に据えず、デイビッド、オペンダをスタメン起用しながら、毎試合異なる前線の構成を試しており、いまだ基本形が固まっていない状態だ。
ヴラホビッチ、デイビッド、オペンダはそれぞれタイプがかなり異なるストライカーであり、その持ち味を活かすために求められる戦術メカニズムも異なっている。その点をどう整理し、チームの基本形を確立していくかが、トゥドル監督にとって最優先の課題だろう。
幸いなのは、守備に関してはある程度計算が立っているところ。PPDA(10.7)はリーグ7位でナポリと同レベル、敵陣でのボール奪取数(1試合平均7.17)はリーグ5位と、プレス強度は際立って高いわけではなく、被シュート数(同12.2本)もリーグ10位だが、被枠内シュート数(同2.5本)、被枠内シュート率(20.5%)はいずれもリーグ2位、PKを除いた被ゴール期待値(xGA、0.75)もリーグ3位と、ゴール前の守りは十分に堅い。
上で触れた通り、インテル、アタランタ、ミランという強豪との対戦が含まれており、しかもインテル戦が4-3の乱戦だったことを考慮に入れれば、評価に値する数字だと言える。
トータルで見ればここからさらに上、優勝戦線への参入を狙えるかどうかは、前線の構成を確立し、それに合わせた戦術の微調整を通して、攻撃のクオリティーを高められるかどうかに懸かっていると言えそうだ。
後編では残る2チーム、ミラン、インテルのミラノ勢について掘り下げたい。
文●片野道郎
【動画】ユベントス対ミラン戦の“主審カメラ”、臨場感あふれる映像が話題!
【記事】データを用いてミラン、インテルを徹底分析「アッレーグリとキブのスタイルは、まったくの対極」「伸びしろが最も大きく見えるのは」セリエA序盤戦総括(後編)【現地発コラム】
ボール支配率(58.6%)、フィールドティルト(61.3%)はいずれもリーグ4位で、強敵相手の試合が多かったにもかかわらず、主導権を握って試合を進める力があることを示している。ただ、敵陣まではスムーズに前進できても、ラスト30m攻略に関しては課題を残しているように見える。
象徴的なのは、ファイナルサードへのパス本数(1試合平均34.8本)ではリーグ4位にもかかわらず、ペナルティーエリアへのパス本数(同7.8本)はトップ5の中で最も少ない7位に留まっていること。これはパスだけでなくキャリー(ドリブルでの持ち上がり)についても同じで、ファイナルサードへの侵入数(同19.2回)はリーグ1位だが、ペナルティーエリアへの侵入数(同3.83回)はリーグ13位。押し込みながらも攻め切れない課題がはっきりと浮かび上がってくる。
シュート数(1試合平均16.0本)、枠内シュート数(同5.33本)はいずれもリーグ3位と、決して悪くないように見える。しかし、そこから生み出されたゴール期待値(同1.21)はリーグ9位。決まる確率の低い強引なシュート、遠い距離からのシュートが多く、攻撃の量に質が伴っていないことは明らかだ。
今シーズンのユベントスは、契約最終年を迎えたドゥシャン・ヴラホビッチを売却し、昨季パリ・サンジェルマンからレンタルしていたランダル・コロ・ムアニを買い取って攻撃の中心に据える構想で移籍マーケットに臨みながら、この2つのオペレーションのどちらも完遂できず、シーズン開幕後も前線の陣容が固まらない困難に直面した。結果的には、リールとの契約満了でフリーになったジョナサン・デイビッドに加え、純粋なセンターフォワードではないロイス・オペンダを獲得。ヴラホビッチは残留という形に落ち着いた。
ここまでのところFW陣で最も好調に見えるのは、CLを含めて8試合で4得点をあげているそのヴラホビッチ。しかし、契約満了前の1月に移籍する可能性も残っているためかトゥドル監督はヴラホビッチを中核に据えず、デイビッド、オペンダをスタメン起用しながら、毎試合異なる前線の構成を試しており、いまだ基本形が固まっていない状態だ。
ヴラホビッチ、デイビッド、オペンダはそれぞれタイプがかなり異なるストライカーであり、その持ち味を活かすために求められる戦術メカニズムも異なっている。その点をどう整理し、チームの基本形を確立していくかが、トゥドル監督にとって最優先の課題だろう。
幸いなのは、守備に関してはある程度計算が立っているところ。PPDA(10.7)はリーグ7位でナポリと同レベル、敵陣でのボール奪取数(1試合平均7.17)はリーグ5位と、プレス強度は際立って高いわけではなく、被シュート数(同12.2本)もリーグ10位だが、被枠内シュート数(同2.5本)、被枠内シュート率(20.5%)はいずれもリーグ2位、PKを除いた被ゴール期待値(xGA、0.75)もリーグ3位と、ゴール前の守りは十分に堅い。
上で触れた通り、インテル、アタランタ、ミランという強豪との対戦が含まれており、しかもインテル戦が4-3の乱戦だったことを考慮に入れれば、評価に値する数字だと言える。
トータルで見ればここからさらに上、優勝戦線への参入を狙えるかどうかは、前線の構成を確立し、それに合わせた戦術の微調整を通して、攻撃のクオリティーを高められるかどうかに懸かっていると言えそうだ。
後編では残る2チーム、ミラン、インテルのミラノ勢について掘り下げたい。
文●片野道郎
【動画】ユベントス対ミラン戦の“主審カメラ”、臨場感あふれる映像が話題!
【記事】データを用いてミラン、インテルを徹底分析「アッレーグリとキブのスタイルは、まったくの対極」「伸びしろが最も大きく見えるのは」セリエA序盤戦総括(後編)【現地発コラム】
関連記事
- データを用いてミラン、インテルを徹底分析「アッレーグリとキブのスタイルは、まったくの対極」「伸びしろが最も大きく見えるのは」セリエA序盤戦総括(後編)【現地発コラム】
- デ・ブライネを「遊軍」として起用するコンテ監督の狙い、ナポリが目指すべき到達点は――「いまはまだ、試行錯誤を重ねている段階」【現地発コラム】
- セリエA首位浮上の好調ミラン「チーム全体の構造が安定した」要因と「改善・向上の余地が残されている」局面とは【現地発コラム】
- “若きタレント2人が活躍した”ユベントスと“主導権を握る意図があった”インテル、スリリングな4-3決着のイタリアダービーで「焦点を当てるべきは」【現地発コラム】
- 2連勝したガットゥーゾ新体制の“収穫と課題”、イタリア代表が直面している“現実”とは「随分と低い目標のように見えるかもしれないが」【現地発コラム】