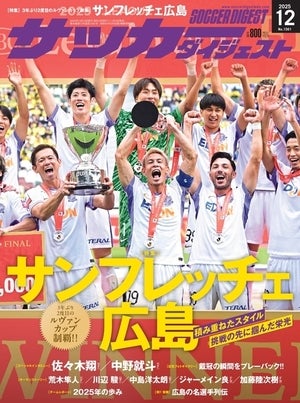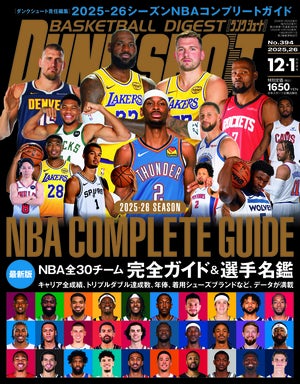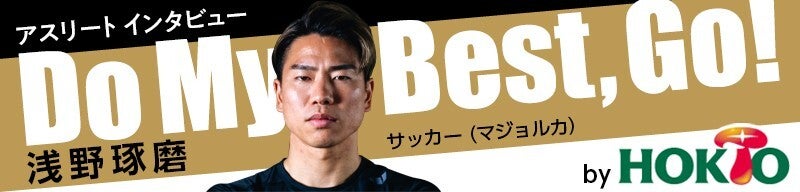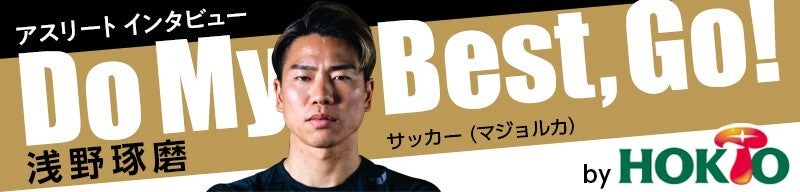そのミランから1ポイント差(4勝2敗・勝点12)で4位につけているのが、同じミラノのライバルで昨シーズン2位のインテル。開幕戦でトリノに5-0と大勝した後、ウディネーゼ、ユベントスに連敗したことで、経験の浅い新監督クリスティアン・キブの手腕を不安視する声が一時的に高まったが、その後はセリエA3試合、チャンピオンズリーグ2試合で5連勝し、結果でその声を封じ込めた。
データに表われているインテルの戦いぶりからは、そのキブがシモーネ・インザーギ前監督から引き継いだ土台に、自らの志向性を少しずつ着実に上乗せしている現状を読み取ることができる。そしてその方向性は、上で見たミランのスタイルとは対極にあると言っていい。
ボール支配率(61.9%)はナポリに僅差で続く2位。フィールドティルト(72.4%)はリーグトップで、最も長い時間相手をゴール前に押し込めて戦っているチームだ。ポゼッションによるゲーム支配そのものは、インザーギの下で戦っていた昨シーズンまでのインテルも同じだった。
しかしインザーギのチームは、守備の局面では重心が低く、プレス強度も決して高いとは言えなかった。一旦相手に持たせてから自陣でのミドルプレスでボールを奪回し、そこから素早く縦に展開するダイレクトアタックでゴールを奪う狙いを持って守っていた、と言ってもいいだろう。
それに対して「キブのインテル」は、守備の局面でもよりアグレッシブになり、チームの重心を高く保ち積極的に前に出てボールを奪おうとする姿勢を、かなり強く持っている。それがはっきりと表れているのが、プレス強度を示すPPDA(9.9)がリーグ3位、攻撃開始点(45.8m)とディフェンスラインの平均位置(54.2m)がリーグで最も高いというデータだ。程度の差はあれ、上で見た「アッレーグリのチーム」に近いコンセプトを持っていたインザーギ時代から、より能動的で積極的、モダンでアグレッシブなスタイルへと舵を切ろうとしていることがわかる。
そしてそれは、攻撃のデータにもはっきりと表われている。ファイナルサードでのパス本数(1試合平均166.8本)と成功数(同131.2本)、ペナルティーエリアへのパス本数(同14.2本)、シュート数(同20.2)、枠内シュート数(同6.17)、ゴール期待値(同2.13)、そして得点数(16)と、ラスト30m攻略にかかわるほとんどの項目で、リーグトップの数字を叩き出しているのだ。
決定機を生み出す主な武器は昨シーズンまでと変わらず、両サイドからの質の高いクロス。クロス本数(同19.2本)、クロス成功率(31.3%)もリーグトップの数字だ。その一方で、ドリブル試行数(同12.5)はリーグ17位、成功数(同5.8)も15位と、ドリブルへの依存度がきわめて低い点も昨シーズン同様。スルーパス(同0.83)もリーグ11位で、ナポリ(同3.5)と比べると4分の1にも満たない数字だ。
可能性を感じさせるのは、ここまで見てきた攻撃力の高さだけでなく、守備の局面においてもデータが際立っているところ。上で触れたプレス強度の高さに象徴されるアグレッシブに前に出る守備は、指揮官の期待通りに機能し始めているように見える。相手に許したファイナルサードへのパス(同20.7本)はリーグで4番目、ペナルティーエリアへのパス(同4.0本)はリーグで3番目に少ない。被シュート数(同8.67本)はリーグ最少だ。
ただし、被枠内シュート数(同3.33)はリーグで少ない方から7番目で、やや比率が高い。しかし、結果的に許した被ゴール期待値(同0.73)はミランに次いで低い。失点そのものも、乱戦だったユベントス戦で全8失点のうち半分を喫しており、残る5試合で4失点は、攻守両局面で積極的に前に出るタイプのチームとしては、決して悪くない数字だ。
総合的に見て、トップ5の中でも現在の順位と比較した時に伸びしろが最も大きいように見えるのは、このインテルではないかと思う。代表ウィーク明けの第7節にはローマ、続く第8節にはナポリと、トップ5チームとの直接対決が待ちかまえている。そこで「キブのインテル」の進化が問われると同時に、その結果によって、順位表にも小さくない変動が出てくるだろう。
文●片野道郎
【動画】ユベントス対ミラン戦、臨場感あふれる映像で話題の“主審カメラ”
【記事】データを用いてナポリ、ローマ、ユベントスを徹底分析「根付きつつあるガスペリーニ哲学」「トゥドル監督にとって最優先の課題は」セリエA序盤戦総括(前編)【現地発コラム】
データに表われているインテルの戦いぶりからは、そのキブがシモーネ・インザーギ前監督から引き継いだ土台に、自らの志向性を少しずつ着実に上乗せしている現状を読み取ることができる。そしてその方向性は、上で見たミランのスタイルとは対極にあると言っていい。
ボール支配率(61.9%)はナポリに僅差で続く2位。フィールドティルト(72.4%)はリーグトップで、最も長い時間相手をゴール前に押し込めて戦っているチームだ。ポゼッションによるゲーム支配そのものは、インザーギの下で戦っていた昨シーズンまでのインテルも同じだった。
しかしインザーギのチームは、守備の局面では重心が低く、プレス強度も決して高いとは言えなかった。一旦相手に持たせてから自陣でのミドルプレスでボールを奪回し、そこから素早く縦に展開するダイレクトアタックでゴールを奪う狙いを持って守っていた、と言ってもいいだろう。
それに対して「キブのインテル」は、守備の局面でもよりアグレッシブになり、チームの重心を高く保ち積極的に前に出てボールを奪おうとする姿勢を、かなり強く持っている。それがはっきりと表れているのが、プレス強度を示すPPDA(9.9)がリーグ3位、攻撃開始点(45.8m)とディフェンスラインの平均位置(54.2m)がリーグで最も高いというデータだ。程度の差はあれ、上で見た「アッレーグリのチーム」に近いコンセプトを持っていたインザーギ時代から、より能動的で積極的、モダンでアグレッシブなスタイルへと舵を切ろうとしていることがわかる。
そしてそれは、攻撃のデータにもはっきりと表われている。ファイナルサードでのパス本数(1試合平均166.8本)と成功数(同131.2本)、ペナルティーエリアへのパス本数(同14.2本)、シュート数(同20.2)、枠内シュート数(同6.17)、ゴール期待値(同2.13)、そして得点数(16)と、ラスト30m攻略にかかわるほとんどの項目で、リーグトップの数字を叩き出しているのだ。
決定機を生み出す主な武器は昨シーズンまでと変わらず、両サイドからの質の高いクロス。クロス本数(同19.2本)、クロス成功率(31.3%)もリーグトップの数字だ。その一方で、ドリブル試行数(同12.5)はリーグ17位、成功数(同5.8)も15位と、ドリブルへの依存度がきわめて低い点も昨シーズン同様。スルーパス(同0.83)もリーグ11位で、ナポリ(同3.5)と比べると4分の1にも満たない数字だ。
可能性を感じさせるのは、ここまで見てきた攻撃力の高さだけでなく、守備の局面においてもデータが際立っているところ。上で触れたプレス強度の高さに象徴されるアグレッシブに前に出る守備は、指揮官の期待通りに機能し始めているように見える。相手に許したファイナルサードへのパス(同20.7本)はリーグで4番目、ペナルティーエリアへのパス(同4.0本)はリーグで3番目に少ない。被シュート数(同8.67本)はリーグ最少だ。
ただし、被枠内シュート数(同3.33)はリーグで少ない方から7番目で、やや比率が高い。しかし、結果的に許した被ゴール期待値(同0.73)はミランに次いで低い。失点そのものも、乱戦だったユベントス戦で全8失点のうち半分を喫しており、残る5試合で4失点は、攻守両局面で積極的に前に出るタイプのチームとしては、決して悪くない数字だ。
総合的に見て、トップ5の中でも現在の順位と比較した時に伸びしろが最も大きいように見えるのは、このインテルではないかと思う。代表ウィーク明けの第7節にはローマ、続く第8節にはナポリと、トップ5チームとの直接対決が待ちかまえている。そこで「キブのインテル」の進化が問われると同時に、その結果によって、順位表にも小さくない変動が出てくるだろう。
文●片野道郎
【動画】ユベントス対ミラン戦、臨場感あふれる映像で話題の“主審カメラ”
【記事】データを用いてナポリ、ローマ、ユベントスを徹底分析「根付きつつあるガスペリーニ哲学」「トゥドル監督にとって最優先の課題は」セリエA序盤戦総括(前編)【現地発コラム】
関連記事
- データを用いてナポリ、ローマ、ユベントスを徹底分析「根付きつつあるガスペリーニ哲学」「トゥドル監督にとって最優先の課題は」セリエA序盤戦総括(前編)【現地発コラム】
- デ・ブライネを「遊軍」として起用するコンテ監督の狙い、ナポリが目指すべき到達点は――「いまはまだ、試行錯誤を重ねている段階」【現地発コラム】
- セリエA首位浮上の好調ミラン「チーム全体の構造が安定した」要因と「改善・向上の余地が残されている」局面とは【現地発コラム】
- “若きタレント2人が活躍した”ユベントスと“主導権を握る意図があった”インテル、スリリングな4-3決着のイタリアダービーで「焦点を当てるべきは」【現地発コラム】
- 2連勝したガットゥーゾ新体制の“収穫と課題”、イタリア代表が直面している“現実”とは「随分と低い目標のように見えるかもしれないが」【現地発コラム】