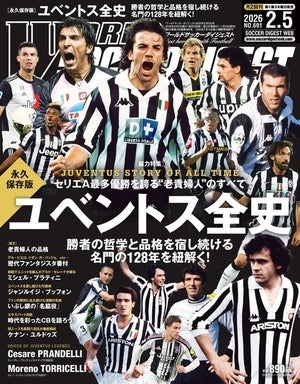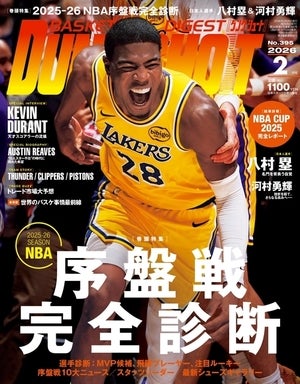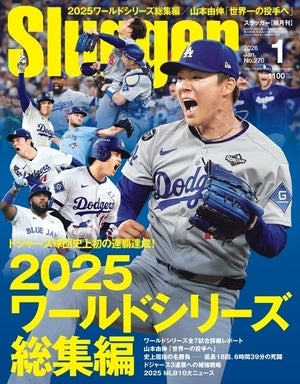テニスは現在、観戦するスポーツとしてだけでなく、プレーするスポーツとしてもランキング上位に入ってきていません。どうすれば、プレー人口が増えるのでしょうか。
競技人口と学校スポーツには密接な関係があります。加えて、幼少期にしていたスポーツは一時期離れたとしても、大人になって再開しやすいものです。つまり、子どもの頃にテニスができる機会を作ることが、競技人口増加の鍵になると考えられます。
これを踏まえると、子どもでも簡単に楽しめて、小学校の授業でも取り入れられる「テニピン」(テニスの面白さを誰もが味わえるように、やさしさを追究して用具とルールをアレンジした新しいゲーム)を広めるのは1つの方法だと思います。
授業のカリキュラムに入れてくれる学校を増やすには、テニス協会の働きかけが重要でしょう。実際、協会と行政が組んだ取り組みが、北海道の東川町で始まっています。1つ成功例があると広げやすいので、今度に期待できるかもしれません。
フランスの方法も参考になると思います。フランスではもう何十年も前に学校のカリキュラムに子どものテニスを入れました。フランステニス連盟が小学校に道具を全て配っています。その代わり、指導するには学校教員でもライセンスを持っていなくてはいけません。
フランスでは学校に限らず、テニスを指導するにはライセンスが必要なのです。ライセンスには登録料が必要であるため、連盟の収入になります。そのお金で道具を提供できると考えれば、正しい使い方と言えるでしょう。
ライセンス保持者の指導を受けられるため、子どもたちは正しい方法を学べます。当然、上達しやすく、テニスは楽しいと思ってくれるでしょう。指導者もライセンスを取った以上は、有効活用したいと考えてテニスを続ける可能性が高くなります。
このような取り組みを続けることで、テニスが文化として根付き、プレー人口も増加していく好循環が生まれればと思います。
文●伊達公子
撮影協力/株式会社SIXINCH.ジャパン
【画像】錦織圭が「テニピン」でジュニア選手を本気で指導!
【画像】錦織、伊達も!日本人トッププロたちの“懐かしジュニア時代”の秘蔵写真をお届け!
【画像】世界4位にまで上り詰めた伊達公子のキャリアを写真で振り返り!
競技人口と学校スポーツには密接な関係があります。加えて、幼少期にしていたスポーツは一時期離れたとしても、大人になって再開しやすいものです。つまり、子どもの頃にテニスができる機会を作ることが、競技人口増加の鍵になると考えられます。
これを踏まえると、子どもでも簡単に楽しめて、小学校の授業でも取り入れられる「テニピン」(テニスの面白さを誰もが味わえるように、やさしさを追究して用具とルールをアレンジした新しいゲーム)を広めるのは1つの方法だと思います。
授業のカリキュラムに入れてくれる学校を増やすには、テニス協会の働きかけが重要でしょう。実際、協会と行政が組んだ取り組みが、北海道の東川町で始まっています。1つ成功例があると広げやすいので、今度に期待できるかもしれません。
フランスの方法も参考になると思います。フランスではもう何十年も前に学校のカリキュラムに子どものテニスを入れました。フランステニス連盟が小学校に道具を全て配っています。その代わり、指導するには学校教員でもライセンスを持っていなくてはいけません。
フランスでは学校に限らず、テニスを指導するにはライセンスが必要なのです。ライセンスには登録料が必要であるため、連盟の収入になります。そのお金で道具を提供できると考えれば、正しい使い方と言えるでしょう。
ライセンス保持者の指導を受けられるため、子どもたちは正しい方法を学べます。当然、上達しやすく、テニスは楽しいと思ってくれるでしょう。指導者もライセンスを取った以上は、有効活用したいと考えてテニスを続ける可能性が高くなります。
このような取り組みを続けることで、テニスが文化として根付き、プレー人口も増加していく好循環が生まれればと思います。
文●伊達公子
撮影協力/株式会社SIXINCH.ジャパン
【画像】錦織圭が「テニピン」でジュニア選手を本気で指導!
【画像】錦織、伊達も!日本人トッププロたちの“懐かしジュニア時代”の秘蔵写真をお届け!
【画像】世界4位にまで上り詰めた伊達公子のキャリアを写真で振り返り!