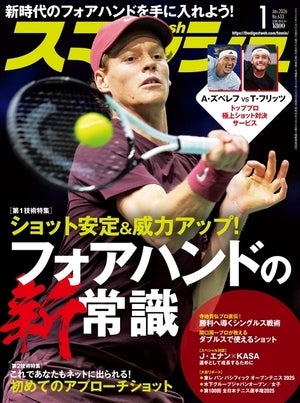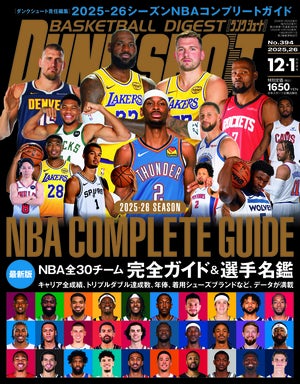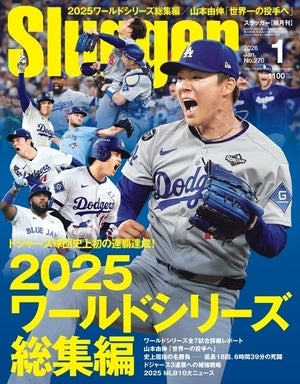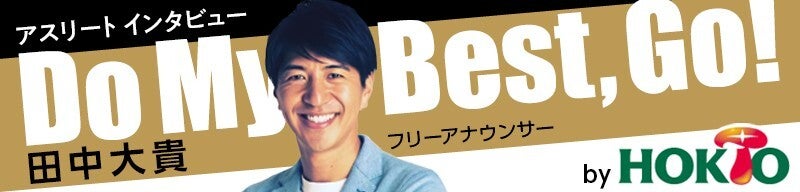そこでアッレーグリは、少なくともここまでの2試合を見る限り、レオンを攻撃の中核に据え、そのタレントを最大限に引き出すことを最優先事項に設定し、それを実現するためにチーム戦術を構築しようとしているように見える。今のところ、その試みはこのまま継続して取り組むに値するだけの可能性を秘めているように見える。
というのも、レオンをCFに据えたシステムは、昨シーズンのミランが最後まで抱えていた大きな欠陥、すなわち守備の不安定さにも一定の解決をもたらしているからだ。その鍵となっているのが、上で触れた攻守で異なる配置を採用する可変システムだ。
攻撃の局面では、自陣から攻撃を組み立てる段階では、4バックの前にリッチ、ユースフ・フォファナ(ユヌス・ムサ)が並ぶ4+2のユニットでボールを動かし、前線では右のアレクシス・サーレマーケルス、左のクリスチャン・プリシックが幅を取り、中央ではレオンと並ぶ最前線までルベン・ロフタス=チークが進出した4-4-2/4-2-4の配置を取る。
後方からショートパスをつないでチーム全体を押し上げることにあまりこだわらず、前が空いたら躊躇なくドリブルで持ち上がったり、前線のロフタス=チークにロングボールを入れ、一気に前進して攻撃を加速ことが意識されている。
敵陣までボールを運んでポゼッションを確立した段階では、左SBのダビデ・バルテサーギが高い位置まで進出し、それに合わせてプリシックが中に入って行くことで3-2-5に配置が変わり、サイドからのクロスや1対1突破、中央でのコンビネーションや単独での打開によってフィニッシュへの道筋を作り出す狙いが見えた。
この攻撃のプロセスにおいて、レオンと同じくらい重要な役割を担っているのがロフタス=チーク。4-3-3のインサイドハーフが前線に進出してCFと同じ高さに並び、ロングボールの受け手になるという役割は、昨シーズンのナポリでスコット・マクトミネイが担ったそれと似通ったものだ。
ピオーリ監督時代に中盤のキープレーヤーとして重要な役割を担っていたが、昨シーズンは序列を落としてベンチを暖める機会が多くなり、影が薄くなっていたのは周知の通り。しかしアッレーグリは、おそらくアントニオ・コンテのナポリからヒントを得たのだろう。その強靭なフィジカル、オープンスペースでの推進力、密集での打開力に注目し、前線に上げて攻撃の基準点として重用することを選んだ。
事実、攻撃の局面で4-3-3から4-4-2/4-2-4、さらには3-2-5へと移行していく可変のメカニズムは、コンテが昨シーズンのナポリで用いていたのと同じだ。そして、ナポリとの共通点はそれだけにとどまらない。さらに顕著に表れているのは、むしろ守備の局面だ。
ボールが奪われた直後、あるいは相手の後方からのビルドアップに対応する際には、ロフタス=チークがそのまま前線に残って4-4-2のコンパクトなミドルブロックを敷き、ボールにプレッシャーをかける。自陣まで押し込まれてローブロックに転じる際は、右ウイングのサーレマーケルスが最終ラインに下がり、フィカヨ・トモリが中央に絞ってマリック・チャウ、ストラヒニャ・パブロビッチとともに3人で中央を固める5バックに転じ、さらにロフタス=チークも中盤に下がることで5-4-1に配置を変更。中央と幅の双方を厚くカバーして相手の侵入を許さない。
アーセナル戦は0-1、リバプール戦は4-2という結果だったが、いずれの失点も守備の綻びというよりは相手のクオリティーが上回ったもので、それ以外に与えた決定機の数も決して多くはなかった。コンパクトなミドルブロック、ローブロックによる組織的な守備は、現時点でもすでに十分な機能性を獲得していると言えるだろう。
右ウイングがローブロック守備時に最終ラインまで下がって5バックを形成するメカニズムは、ナポリでマッテオ・ポリターノが担っている機能とまったく同じ。サーレマーケルスは、かつてミランの強化責任者だったマルディーニが、右サイドバックでの起用も視野に入れて獲得した選手だ。昨シーズンのレンタル先だったローマでウイングバックとして活躍したのを見てもわかるように、水準以上の攻撃性能に加えて、ピッチの縦幅100メートルを1人でカバーできる運動量と持久力も備えている。その点でこのタスクはまさに適材適所と言える。
元々アッレーグリは、特定のシステムや戦術に強いこだわりを持つタイプの監督ではなく、むしろ抱える選手それぞれの持ち味を最大限に引き出すために、システムや戦術をオーダーメイドで設計するタイプ。得点するよりも失点しないことに重きを置き、守備の局面では組織的な戦術メカニズムを重視する一方で、攻撃の局面では個のクオリティーに依存する度合いが高いという点で、イタリアサッカーの伝統的な価値観と哲学を体現するタイプでもある。
そんなアッレーグリが、明らかにコンテから拝借したアイデアをミランの陣容にうまく適用し、レオンという希有な攻撃のタレントの持ち味を最大限に引き出しつつ、ロフタス=チークを活性化。サーレマーケルスのマルチな能力も利用しながら、戦術的な辻褄をしっかり合わせて攻守のバランスを確保したチームを構築しつつあるという現状は、非常に興味深いものだ。
現時点ではまだ2試合、しかも格上相手にボールを委ねての堅守&カウンターが機能しただけであり、セリエAの大半の試合に見られるような、自らがボールを持ち主導権を握って戦う展開でチームがどう機能するかなど、未知数は少なくない。それも含めて、チームが今後どのような進化のプロセスを辿るのかは注目に値する。
文●片野道郎
【記事】セリエAトップ10のうち7チームが監督交代、注目はローマ新指揮官として「キャリア最後の挑戦」に臨むガスペリーニの手腕【現地発コラム】
【記事】キブ新体制で再出発のインテル、トゥドル監督を続投させたユベントス、クラブW杯で見せたチーム作りの注目ポイント【現地発コラム】
というのも、レオンをCFに据えたシステムは、昨シーズンのミランが最後まで抱えていた大きな欠陥、すなわち守備の不安定さにも一定の解決をもたらしているからだ。その鍵となっているのが、上で触れた攻守で異なる配置を採用する可変システムだ。
攻撃の局面では、自陣から攻撃を組み立てる段階では、4バックの前にリッチ、ユースフ・フォファナ(ユヌス・ムサ)が並ぶ4+2のユニットでボールを動かし、前線では右のアレクシス・サーレマーケルス、左のクリスチャン・プリシックが幅を取り、中央ではレオンと並ぶ最前線までルベン・ロフタス=チークが進出した4-4-2/4-2-4の配置を取る。
後方からショートパスをつないでチーム全体を押し上げることにあまりこだわらず、前が空いたら躊躇なくドリブルで持ち上がったり、前線のロフタス=チークにロングボールを入れ、一気に前進して攻撃を加速ことが意識されている。
敵陣までボールを運んでポゼッションを確立した段階では、左SBのダビデ・バルテサーギが高い位置まで進出し、それに合わせてプリシックが中に入って行くことで3-2-5に配置が変わり、サイドからのクロスや1対1突破、中央でのコンビネーションや単独での打開によってフィニッシュへの道筋を作り出す狙いが見えた。
この攻撃のプロセスにおいて、レオンと同じくらい重要な役割を担っているのがロフタス=チーク。4-3-3のインサイドハーフが前線に進出してCFと同じ高さに並び、ロングボールの受け手になるという役割は、昨シーズンのナポリでスコット・マクトミネイが担ったそれと似通ったものだ。
ピオーリ監督時代に中盤のキープレーヤーとして重要な役割を担っていたが、昨シーズンは序列を落としてベンチを暖める機会が多くなり、影が薄くなっていたのは周知の通り。しかしアッレーグリは、おそらくアントニオ・コンテのナポリからヒントを得たのだろう。その強靭なフィジカル、オープンスペースでの推進力、密集での打開力に注目し、前線に上げて攻撃の基準点として重用することを選んだ。
事実、攻撃の局面で4-3-3から4-4-2/4-2-4、さらには3-2-5へと移行していく可変のメカニズムは、コンテが昨シーズンのナポリで用いていたのと同じだ。そして、ナポリとの共通点はそれだけにとどまらない。さらに顕著に表れているのは、むしろ守備の局面だ。
ボールが奪われた直後、あるいは相手の後方からのビルドアップに対応する際には、ロフタス=チークがそのまま前線に残って4-4-2のコンパクトなミドルブロックを敷き、ボールにプレッシャーをかける。自陣まで押し込まれてローブロックに転じる際は、右ウイングのサーレマーケルスが最終ラインに下がり、フィカヨ・トモリが中央に絞ってマリック・チャウ、ストラヒニャ・パブロビッチとともに3人で中央を固める5バックに転じ、さらにロフタス=チークも中盤に下がることで5-4-1に配置を変更。中央と幅の双方を厚くカバーして相手の侵入を許さない。
アーセナル戦は0-1、リバプール戦は4-2という結果だったが、いずれの失点も守備の綻びというよりは相手のクオリティーが上回ったもので、それ以外に与えた決定機の数も決して多くはなかった。コンパクトなミドルブロック、ローブロックによる組織的な守備は、現時点でもすでに十分な機能性を獲得していると言えるだろう。
右ウイングがローブロック守備時に最終ラインまで下がって5バックを形成するメカニズムは、ナポリでマッテオ・ポリターノが担っている機能とまったく同じ。サーレマーケルスは、かつてミランの強化責任者だったマルディーニが、右サイドバックでの起用も視野に入れて獲得した選手だ。昨シーズンのレンタル先だったローマでウイングバックとして活躍したのを見てもわかるように、水準以上の攻撃性能に加えて、ピッチの縦幅100メートルを1人でカバーできる運動量と持久力も備えている。その点でこのタスクはまさに適材適所と言える。
元々アッレーグリは、特定のシステムや戦術に強いこだわりを持つタイプの監督ではなく、むしろ抱える選手それぞれの持ち味を最大限に引き出すために、システムや戦術をオーダーメイドで設計するタイプ。得点するよりも失点しないことに重きを置き、守備の局面では組織的な戦術メカニズムを重視する一方で、攻撃の局面では個のクオリティーに依存する度合いが高いという点で、イタリアサッカーの伝統的な価値観と哲学を体現するタイプでもある。
そんなアッレーグリが、明らかにコンテから拝借したアイデアをミランの陣容にうまく適用し、レオンという希有な攻撃のタレントの持ち味を最大限に引き出しつつ、ロフタス=チークを活性化。サーレマーケルスのマルチな能力も利用しながら、戦術的な辻褄をしっかり合わせて攻守のバランスを確保したチームを構築しつつあるという現状は、非常に興味深いものだ。
現時点ではまだ2試合、しかも格上相手にボールを委ねての堅守&カウンターが機能しただけであり、セリエAの大半の試合に見られるような、自らがボールを持ち主導権を握って戦う展開でチームがどう機能するかなど、未知数は少なくない。それも含めて、チームが今後どのような進化のプロセスを辿るのかは注目に値する。
文●片野道郎
【記事】セリエAトップ10のうち7チームが監督交代、注目はローマ新指揮官として「キャリア最後の挑戦」に臨むガスペリーニの手腕【現地発コラム】
【記事】キブ新体制で再出発のインテル、トゥドル監督を続投させたユベントス、クラブW杯で見せたチーム作りの注目ポイント【現地発コラム】
関連記事
- セリエAトップ10のうち7チームが監督交代、注目はローマ新指揮官として「キャリア最後の挑戦」に臨むガスペリーニの手腕【現地発コラム】
- キブ新体制で再出発のインテル、トゥドル監督を続投させたユベントス、クラブW杯で見せたチーム作りの注目ポイント【現地発コラム】
- イタリア代表新監督ガットゥーゾは、「帰属意識」「結束」「ファミリー」を柱に「敵陣でボールを保持し、ゴールを奪うチーム」を目指す【現地発コラム】
- 持てる力を限界まで絞り出した「コンテの手腕がナポリの“勝因”」2位インテルとの隔たりは「微妙な差」【現地発コラム】
- パリSGに0-5と歴史的大敗…圧倒的強度のプレッシングに「手も足も出なかった」インテル、「しかし、今シーズンの評価はむしろ…」【現地発コラム】