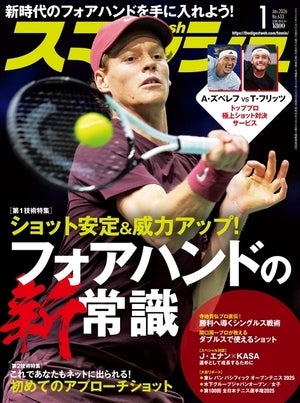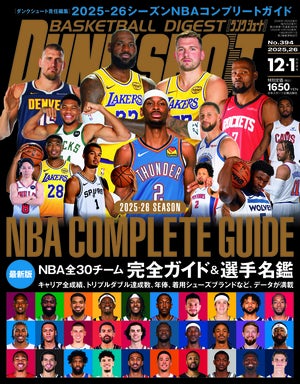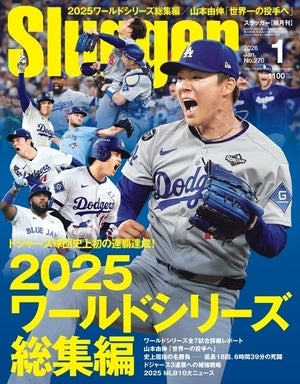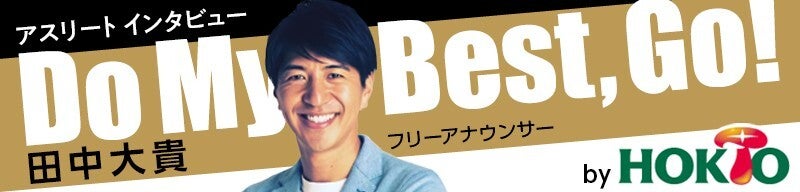続くイスラエル戦は、冒頭で見た可能性と課題があからさまな形で衆目に晒された試合だった。ガットゥーゾ監督は、ザッカーニが軽い故障で出場できなくなったこともあり、代わりにウイングではなくセントラルMFのマヌエル・ロカテッリを入れた布陣をピッチに送った。
スタート時点におけるピッチ上の配置も、エストニア戦のそれから左ウイングがいなくなった代わりに中盤の底にロカテッリが入り、前線は2トップが中央に並んでポリターノが右ウイングという、左右非対称の奇妙な4-3-3。
GK:ドンナルンマ
DF:ディ・ロレンツォ、マンチーニ、バストーニ、ディマルコ
MF:バレッラ、ロカテッリ、トナーリ
FW:ポリターノ、レテギ、ケーン
右サイドに人数をかけ、左サイド前方に大きなスペースを残すこの配置の狙いはおそらく、右から攻撃を組み立てて相手の守備を一方のサイドに偏らせ、大きなサイドチェンジからディマルコを使って一気に前進することにあったと思われる。
しかし実際には、イスラエルの強烈なマンツーマンハイプレスの前にビルドアップが詰まる場面が多く、効果的なサイドチェンジはほとんど見られない。逆に守備の局面でこの左右非対称の配置がもたらす左サイドのスペースを使われ、困難に陥る場面が頻発することになった。
16分にロカテッリのオウンゴールで許した先制点も、左サイドでディマルコが数的不利に陥り後手に回ってクロスを許しただけでなく、同時に外に引き出された左CBバストーニが空けた左ポケットに入り込まれたことが原因だった。
イタリアの守備は、大枠はゾーンディフェンスだが、ラインを維持するよりもゾーン内の人を捉まえることを優先する「ゾーン内マンマーク」の原則を採用していた。これは、ガットゥーゾ監督が試合後の会見で説明していたように、セリエAの多くのチームがこの守り方を用いており、選手が慣れていることが大きな理由だ。
イスラエルはこれに対して、4-2-3-1の「前4人」が流動的に動くこと、とりわけトップ下のオスカル・グロークとCFダン・ビトンが外に流れる動きを繰り返すことで、イタリアのCBを動かして最終ラインにギャップを作り出し、後方から攻め上がってきたMFがそのスペースを使うことでイタリアを困難に陥れた。
左右非対称配置がもたらす左サイドのスペース問題は、先制点を許した後に、サンドロ・トナーリを左サイドに開かせると同時にポリターノを一列下げて、左右対称の4-4-2としたことで解決した。
しかし、人に強く基準を置く「ゾーン内マンマーク」が最終ラインにギャップやスペースを作り出す問題は、試合を通してイタリアを苦しめることになる。ガットゥーゾ監督が試合終盤まで、事あるごとにCBのジャンルカ・マンチーニとアレッサンドロ・バストーニに指示を送り続けていた事実は象徴的だ。
文字通り「ゆるゆる」だったセットプレーの守備も含めて、このイスラエル戦でのディフェンスは、目を覆いたくなるような脆さだった。守備の局面における基本的な配置、とりわけ基本となる原則(人とスペースのどちらに強く基準を置くか)の明確化は、ガットゥーゾ監督が早急に取り組み、解決すべき最優先課題と言えるだろう。
攻撃の局面に関しては、後方からのビルドアップがマンツーマンハイプレスの前に行き詰まる場面が多かった一方で、前線の2トップを基準点とするダイレクトアタックが効果的に機能して、それを埋め合わせる格好になった。
マンツーマンハイプレスは、前線で同数のプレスを仕掛けるために、後方でも2CB対2トップの数的均衡というリスクを受け入れることで成り立っている。レテギとケーンはともにフィジカルコンタクトに強いだけでなくスピードもあり、相手2ライン(DFとMF)間に引く動きでDFを背負ってポストとして機能することも、裏のスペースをアタックすることもできる。
しかも一緒にプレーするのは今回が事実上初めてとは思えないほど呼吸が合っており、常に近い位置にポジションを取って互いの動きを「感じ」ながら補完的な連携を見せていた。
イタリアがイスラエル戦で決めた5得点のうち、最初の3点はいずれもレテギがポストプレーによる落としでケーン(1点目と2点目)、ポリターノ(3点目)をアシストしたもの。エストニア戦でも先制点はレテギ→ケーンのホットラインから生まれており、さらにレテギは2得点を挙げている。
近年の欧州サッカーは1トップのシステムが主流になっており、スピードとパワーを備えたストライカーが前線に2枚並び、2CBにデュエルを挑む攻撃には、どのチームもあまり慣れていない。それも含め、この2トップは「ガットゥーゾのイタリア」の最大の武器であり、今後のチーム構築の出発点かつ基準点となることは間違いなさそうだ。
W杯予選でイタリアは10月にあらためてエストニア、イスラエルと戦い、11月にモルドバ、そしてノルウェーと対戦する。たとえ最後の直接対決を含めた全試合に勝ったとしても、ノルウェーが万が一エストニアかイスラエルに勝ち点を取りこぼさない限り、イタリアは3大会連続でプレーオフに回る可能性が濃厚になっている。
そこまでを視野に入れて考えれば、ガットゥーゾ監督は今後、3月に行なわれるそのプレーオフに焦点を合わせてチームを構築していくアプローチを取るべきだろう。具体的には、10月、11月の4試合を通して、レテギ、ケーンの2トップを攻守両局面で支えられるシステム(4-4-2または3-5-2が現実的な選択肢だろう)と、基本的な守備のプレー原則(人かスペースか)を明確にして、攻守のバランスを見出し、チームのアイデンティティーを再確立すること。
ノルウェー、そしてプレーオフで対戦するであろう質の高い中堅国(スロバキア、スウェーデン、トルコ、スコットランド、ハンガリー、ポーランド、オーストリア、セルビアといった国々)と互角以上に戦えるレベルまで、チームの完成度を高められるかどうかが勝負である。
4年前にEUROを制したことを考えれば、随分と低い目標のように見えるかもしれない。しかしこれが、過去2大会連続でプレーオフ敗退を喫してきたイタリアが直面している現実なのである。
文●片野道郎
【動画】ガットゥーゾ新監督率いるイタリア代表が、エストニアに5-0、イスラエルに5-4で勝利
【記事】イタリア代表新監督ガットゥーゾは、「帰属意識」「結束」「ファミリー」を柱に「敵陣でボールを保持し、ゴールを奪うチーム」を目指す【現地発コラム】
スタート時点におけるピッチ上の配置も、エストニア戦のそれから左ウイングがいなくなった代わりに中盤の底にロカテッリが入り、前線は2トップが中央に並んでポリターノが右ウイングという、左右非対称の奇妙な4-3-3。
GK:ドンナルンマ
DF:ディ・ロレンツォ、マンチーニ、バストーニ、ディマルコ
MF:バレッラ、ロカテッリ、トナーリ
FW:ポリターノ、レテギ、ケーン
右サイドに人数をかけ、左サイド前方に大きなスペースを残すこの配置の狙いはおそらく、右から攻撃を組み立てて相手の守備を一方のサイドに偏らせ、大きなサイドチェンジからディマルコを使って一気に前進することにあったと思われる。
しかし実際には、イスラエルの強烈なマンツーマンハイプレスの前にビルドアップが詰まる場面が多く、効果的なサイドチェンジはほとんど見られない。逆に守備の局面でこの左右非対称の配置がもたらす左サイドのスペースを使われ、困難に陥る場面が頻発することになった。
16分にロカテッリのオウンゴールで許した先制点も、左サイドでディマルコが数的不利に陥り後手に回ってクロスを許しただけでなく、同時に外に引き出された左CBバストーニが空けた左ポケットに入り込まれたことが原因だった。
イタリアの守備は、大枠はゾーンディフェンスだが、ラインを維持するよりもゾーン内の人を捉まえることを優先する「ゾーン内マンマーク」の原則を採用していた。これは、ガットゥーゾ監督が試合後の会見で説明していたように、セリエAの多くのチームがこの守り方を用いており、選手が慣れていることが大きな理由だ。
イスラエルはこれに対して、4-2-3-1の「前4人」が流動的に動くこと、とりわけトップ下のオスカル・グロークとCFダン・ビトンが外に流れる動きを繰り返すことで、イタリアのCBを動かして最終ラインにギャップを作り出し、後方から攻め上がってきたMFがそのスペースを使うことでイタリアを困難に陥れた。
左右非対称配置がもたらす左サイドのスペース問題は、先制点を許した後に、サンドロ・トナーリを左サイドに開かせると同時にポリターノを一列下げて、左右対称の4-4-2としたことで解決した。
しかし、人に強く基準を置く「ゾーン内マンマーク」が最終ラインにギャップやスペースを作り出す問題は、試合を通してイタリアを苦しめることになる。ガットゥーゾ監督が試合終盤まで、事あるごとにCBのジャンルカ・マンチーニとアレッサンドロ・バストーニに指示を送り続けていた事実は象徴的だ。
文字通り「ゆるゆる」だったセットプレーの守備も含めて、このイスラエル戦でのディフェンスは、目を覆いたくなるような脆さだった。守備の局面における基本的な配置、とりわけ基本となる原則(人とスペースのどちらに強く基準を置くか)の明確化は、ガットゥーゾ監督が早急に取り組み、解決すべき最優先課題と言えるだろう。
攻撃の局面に関しては、後方からのビルドアップがマンツーマンハイプレスの前に行き詰まる場面が多かった一方で、前線の2トップを基準点とするダイレクトアタックが効果的に機能して、それを埋め合わせる格好になった。
マンツーマンハイプレスは、前線で同数のプレスを仕掛けるために、後方でも2CB対2トップの数的均衡というリスクを受け入れることで成り立っている。レテギとケーンはともにフィジカルコンタクトに強いだけでなくスピードもあり、相手2ライン(DFとMF)間に引く動きでDFを背負ってポストとして機能することも、裏のスペースをアタックすることもできる。
しかも一緒にプレーするのは今回が事実上初めてとは思えないほど呼吸が合っており、常に近い位置にポジションを取って互いの動きを「感じ」ながら補完的な連携を見せていた。
イタリアがイスラエル戦で決めた5得点のうち、最初の3点はいずれもレテギがポストプレーによる落としでケーン(1点目と2点目)、ポリターノ(3点目)をアシストしたもの。エストニア戦でも先制点はレテギ→ケーンのホットラインから生まれており、さらにレテギは2得点を挙げている。
近年の欧州サッカーは1トップのシステムが主流になっており、スピードとパワーを備えたストライカーが前線に2枚並び、2CBにデュエルを挑む攻撃には、どのチームもあまり慣れていない。それも含め、この2トップは「ガットゥーゾのイタリア」の最大の武器であり、今後のチーム構築の出発点かつ基準点となることは間違いなさそうだ。
W杯予選でイタリアは10月にあらためてエストニア、イスラエルと戦い、11月にモルドバ、そしてノルウェーと対戦する。たとえ最後の直接対決を含めた全試合に勝ったとしても、ノルウェーが万が一エストニアかイスラエルに勝ち点を取りこぼさない限り、イタリアは3大会連続でプレーオフに回る可能性が濃厚になっている。
そこまでを視野に入れて考えれば、ガットゥーゾ監督は今後、3月に行なわれるそのプレーオフに焦点を合わせてチームを構築していくアプローチを取るべきだろう。具体的には、10月、11月の4試合を通して、レテギ、ケーンの2トップを攻守両局面で支えられるシステム(4-4-2または3-5-2が現実的な選択肢だろう)と、基本的な守備のプレー原則(人かスペースか)を明確にして、攻守のバランスを見出し、チームのアイデンティティーを再確立すること。
ノルウェー、そしてプレーオフで対戦するであろう質の高い中堅国(スロバキア、スウェーデン、トルコ、スコットランド、ハンガリー、ポーランド、オーストリア、セルビアといった国々)と互角以上に戦えるレベルまで、チームの完成度を高められるかどうかが勝負である。
4年前にEUROを制したことを考えれば、随分と低い目標のように見えるかもしれない。しかしこれが、過去2大会連続でプレーオフ敗退を喫してきたイタリアが直面している現実なのである。
文●片野道郎
【動画】ガットゥーゾ新監督率いるイタリア代表が、エストニアに5-0、イスラエルに5-4で勝利
【記事】イタリア代表新監督ガットゥーゾは、「帰属意識」「結束」「ファミリー」を柱に「敵陣でボールを保持し、ゴールを奪うチーム」を目指す【現地発コラム】
関連記事
- アッレーグリ新体制のミランを深掘り「コンテのナポリから拝借したアイデア」「レオンと同じくらい重要な役割を担っているのが」【現地発コラム】
- セリエAトップ10のうち7チームが監督交代、注目はローマ新指揮官として「キャリア最後の挑戦」に臨むガスペリーニの手腕【現地発コラム】
- キブ新体制で再出発のインテル、トゥドル監督を続投させたユベントス、クラブW杯で見せたチーム作りの注目ポイント【現地発コラム】
- イタリア代表新監督ガットゥーゾは、「帰属意識」「結束」「ファミリー」を柱に「敵陣でボールを保持し、ゴールを奪うチーム」を目指す【現地発コラム】
- イタリア代表が大混乱…前日解任のスパレッティ監督がチームを指揮→後任決まらずW杯1年前に指揮官不在の異例事態【現地発コラム】