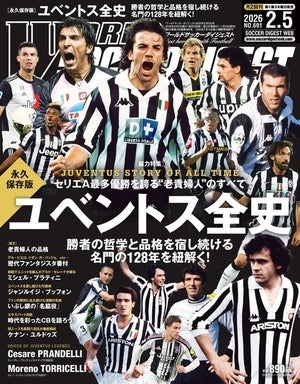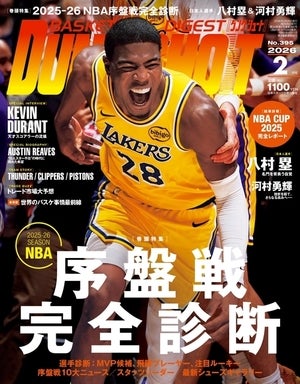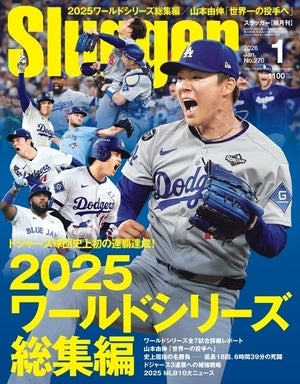開幕から6試合を消化して10月の代表ウィークを迎えた2025-26シーズンのセリエA序盤戦総括、後編では3、4位を占めるミラノ勢2チームについて掘り下げたい。目先の結果よりもピッチ上でのチームのパフォーマンスに注目し、客観的な判断・評価の材料としてデータを使いながら見ていくのは前編と同じ。データは『Opta Analyst』、『FBref』、『MARKSTATS』という3つのサイトを参照している。
現在の順位表でトップ5を占めるビッグクラブの中でも、変化の幅が最も大きかったのはミランだろう。監督にマッシミリアーノ・アッレーグリが11年ぶりに復帰し、陣容も登録メンバーの半分近くが入れ替わった。昨季までチームの看板だったティジャニ・ラインデルス、テオ・エルナンデズが去り、ルカ・モドリッチ、アドリアン・ラビオというビッグネームが加入したことで、チームの表情は一変した感がある。
ここまで6試合の成績は4勝1分け1敗(勝点13)で首位から2ポイント差の3位。開幕戦で昇格組のクレモネーゼに敗れる波乱があったものの、移籍期限ギリギリに獲得したラビオが加わって中盤の安定度が攻守両局面で大きく高まった9月以降は、結果と内容の両面で安定した戦いぶりを見せている。
データに表われているのは、アッレーグリが打ち出しているサッカーが、上位陣の中で唯一、まったく毛色が異なっている点だ。他の4チーム(ナポリ、ローマ、ユベントス、インテル)が60%近いボール支配率を記録する中、ミランのそれは50.6%(リーグ9位)止まり。
アタッキングサード限定の支配率であるフィールドティルトは44.7%(リーグ15位)で、むしろ相手に押し込まれている時間が長いことを示している。このデータからだけでも、ボールだけでなく地域も相手に明け渡して受け身で戦う、いかにもアッレーグリらしいスタイルをはっきりと見て取ることができる。
そうしたスタイルは守備の局面でさらに顕著になる。ディフェンスラインの平均位置(43.8m)は、リーグで下から4番目という低さ。プレス強度を示すPPDA(相手のボール保持機会あたり許したパス本数)は18.6とリーグ最下位で、プレッシングによって能動的、積極的にボールを奪回する意志そのものを持っていないことを示している。もちろんこれは明確な戦術的選択だ。
ボールを相手に委ね、重心を低く構えて攻撃を受け止めるチームの多くは、自陣でボールを奪った後一気に縦に展開し、カウンターアタックでゴールを奪おうとする傾向が強い。しかしミランはそうではない。自陣でポゼッションを確立し、前進すること以上に嫌な形でボールを失わないことに優先順位を置いた慎重なパス回しで、時間をかけて攻撃する。ボール保持1回あたりの平均前進スピード(1.51)はリーグ最下位、全パスに占める後方へのパス数比率はリーグで2番目に高いというデータは象徴的だ。
ペースが遅くリスクを冒そうとしない試合運びであり、必然的に攻撃のボリューム自体も限られてくる。ファイナルサードでのパス総数(1試合平均105.3本)はリーグ8位、ファイナルサードへのパス本数(同28.5本)はリーグ9位に留まる。
しかし、ファイナルサードでのパス成功総数(同80.3本)、ペナルティーエリアへのパス本数(同8.2本)はいずれもリーグ5位で、攻撃の「質」に話を限れば、トップ5の他チームとほぼ遜色のない数字が出てくる。シュート数(同14.0本)は7位、枠内シュート数(同4.7本)は8位だが、そこから生み出したゴール期待値(xG、同1.45)はインテル、ナポリに次いでリーグ3位と、ユベントスやローマを上回っているのだ。
ラスト30m攻略の主な武器はドリブル突破(1試合平均成功数7.0はリーグ6位)とスルーパス(同2.5はリーグ2位)。一方、クロス(同13.3本)はリーグ16位と少ない。これらのデータには、慎重なポゼッションから相手の隙を衝いて縦に攻撃を加速し、一気にフィニッシュに持ち込むミランのスタイルが表われている。第6節のユベントス戦で後半開始から間もなく、モドリッチが裏に走り込んだ前線のサンティアゴ・ヒメネスに送り込んだ浮き球の縦パスはその典型だ。
一方、すでに見た通りプレッシングを放棄して低く構える受け身の守備は、6試合で3失点(リーグ2位)という数字が示す通りきわめて堅い。相手に許したファイナルサードへのパス本数(同36.3)はリーグで3番目、ペナルティーエリアへのパス本数(同8.2)はリーグで4番目に多い数字だが、被シュート数(同9.33)はリーグで2番目に少なく、許した被ゴール期待値(xGA、同0.68)は何とリーグで最も低い数字なのだ。
これらから見えてくるのは、あえて受け身で戦うことを選びながら、ボールを持たずに試合をコントロールし、回数は多くないが質の高いチャンスを作り出してそれをしっかりものにし、勝点を着実に積み上げていく、つまらないが手堅いしたたかなチーム像だ。まさしく「アッレーグリのチーム」そのものである。
現在の順位表でトップ5を占めるビッグクラブの中でも、変化の幅が最も大きかったのはミランだろう。監督にマッシミリアーノ・アッレーグリが11年ぶりに復帰し、陣容も登録メンバーの半分近くが入れ替わった。昨季までチームの看板だったティジャニ・ラインデルス、テオ・エルナンデズが去り、ルカ・モドリッチ、アドリアン・ラビオというビッグネームが加入したことで、チームの表情は一変した感がある。
ここまで6試合の成績は4勝1分け1敗(勝点13)で首位から2ポイント差の3位。開幕戦で昇格組のクレモネーゼに敗れる波乱があったものの、移籍期限ギリギリに獲得したラビオが加わって中盤の安定度が攻守両局面で大きく高まった9月以降は、結果と内容の両面で安定した戦いぶりを見せている。
データに表われているのは、アッレーグリが打ち出しているサッカーが、上位陣の中で唯一、まったく毛色が異なっている点だ。他の4チーム(ナポリ、ローマ、ユベントス、インテル)が60%近いボール支配率を記録する中、ミランのそれは50.6%(リーグ9位)止まり。
アタッキングサード限定の支配率であるフィールドティルトは44.7%(リーグ15位)で、むしろ相手に押し込まれている時間が長いことを示している。このデータからだけでも、ボールだけでなく地域も相手に明け渡して受け身で戦う、いかにもアッレーグリらしいスタイルをはっきりと見て取ることができる。
そうしたスタイルは守備の局面でさらに顕著になる。ディフェンスラインの平均位置(43.8m)は、リーグで下から4番目という低さ。プレス強度を示すPPDA(相手のボール保持機会あたり許したパス本数)は18.6とリーグ最下位で、プレッシングによって能動的、積極的にボールを奪回する意志そのものを持っていないことを示している。もちろんこれは明確な戦術的選択だ。
ボールを相手に委ね、重心を低く構えて攻撃を受け止めるチームの多くは、自陣でボールを奪った後一気に縦に展開し、カウンターアタックでゴールを奪おうとする傾向が強い。しかしミランはそうではない。自陣でポゼッションを確立し、前進すること以上に嫌な形でボールを失わないことに優先順位を置いた慎重なパス回しで、時間をかけて攻撃する。ボール保持1回あたりの平均前進スピード(1.51)はリーグ最下位、全パスに占める後方へのパス数比率はリーグで2番目に高いというデータは象徴的だ。
ペースが遅くリスクを冒そうとしない試合運びであり、必然的に攻撃のボリューム自体も限られてくる。ファイナルサードでのパス総数(1試合平均105.3本)はリーグ8位、ファイナルサードへのパス本数(同28.5本)はリーグ9位に留まる。
しかし、ファイナルサードでのパス成功総数(同80.3本)、ペナルティーエリアへのパス本数(同8.2本)はいずれもリーグ5位で、攻撃の「質」に話を限れば、トップ5の他チームとほぼ遜色のない数字が出てくる。シュート数(同14.0本)は7位、枠内シュート数(同4.7本)は8位だが、そこから生み出したゴール期待値(xG、同1.45)はインテル、ナポリに次いでリーグ3位と、ユベントスやローマを上回っているのだ。
ラスト30m攻略の主な武器はドリブル突破(1試合平均成功数7.0はリーグ6位)とスルーパス(同2.5はリーグ2位)。一方、クロス(同13.3本)はリーグ16位と少ない。これらのデータには、慎重なポゼッションから相手の隙を衝いて縦に攻撃を加速し、一気にフィニッシュに持ち込むミランのスタイルが表われている。第6節のユベントス戦で後半開始から間もなく、モドリッチが裏に走り込んだ前線のサンティアゴ・ヒメネスに送り込んだ浮き球の縦パスはその典型だ。
一方、すでに見た通りプレッシングを放棄して低く構える受け身の守備は、6試合で3失点(リーグ2位)という数字が示す通りきわめて堅い。相手に許したファイナルサードへのパス本数(同36.3)はリーグで3番目、ペナルティーエリアへのパス本数(同8.2)はリーグで4番目に多い数字だが、被シュート数(同9.33)はリーグで2番目に少なく、許した被ゴール期待値(xGA、同0.68)は何とリーグで最も低い数字なのだ。
これらから見えてくるのは、あえて受け身で戦うことを選びながら、ボールを持たずに試合をコントロールし、回数は多くないが質の高いチャンスを作り出してそれをしっかりものにし、勝点を着実に積み上げていく、つまらないが手堅いしたたかなチーム像だ。まさしく「アッレーグリのチーム」そのものである。
関連記事
- データを用いてナポリ、ローマ、ユベントスを徹底分析「根付きつつあるガスペリーニ哲学」「トゥドル監督にとって最優先の課題は」セリエA序盤戦総括(前編)【現地発コラム】
- デ・ブライネを「遊軍」として起用するコンテ監督の狙い、ナポリが目指すべき到達点は――「いまはまだ、試行錯誤を重ねている段階」【現地発コラム】
- セリエA首位浮上の好調ミラン「チーム全体の構造が安定した」要因と「改善・向上の余地が残されている」局面とは【現地発コラム】
- “若きタレント2人が活躍した”ユベントスと“主導権を握る意図があった”インテル、スリリングな4-3決着のイタリアダービーで「焦点を当てるべきは」【現地発コラム】
- 2連勝したガットゥーゾ新体制の“収穫と課題”、イタリア代表が直面している“現実”とは「随分と低い目標のように見えるかもしれないが」【現地発コラム】