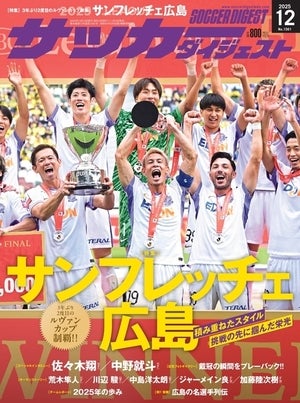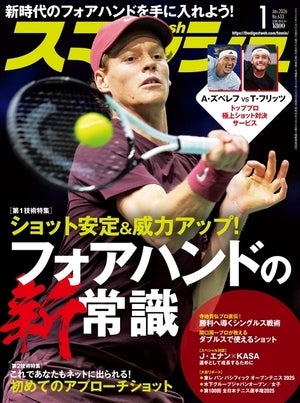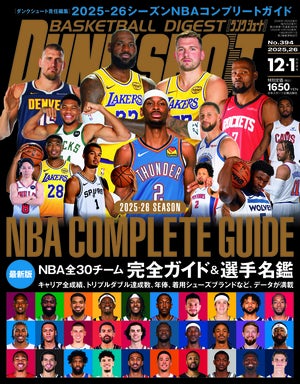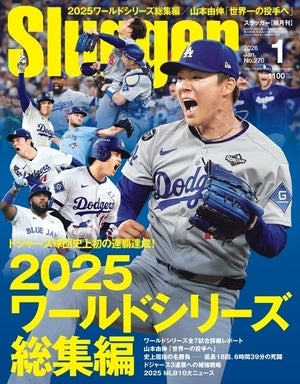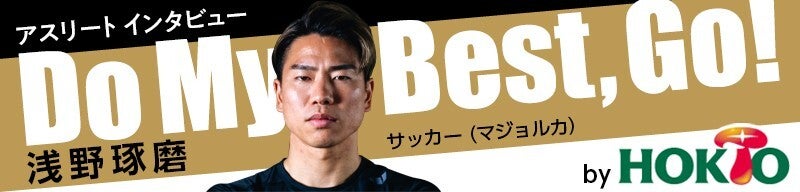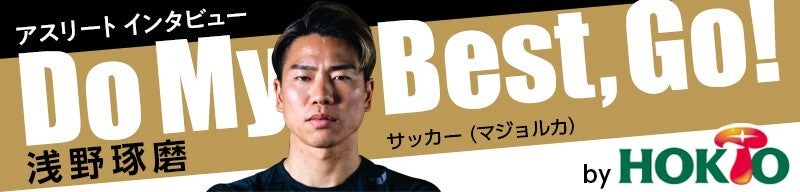一方のユベントスは、3月にチアゴ・モッタ前監督を解任した際、シーズンの残り試合およびクラブW杯に期間を限定した「つなぎ」の監督として起用したイーゴル・トゥドルの下で、この大会を戦っている。これは、新シーズンに向けて別の監督(具体的にはアントニオ・コンテ)を招聘したい思惑があったためだが、最終的にコンテがナポリ残留を決断。それを受けてクラブは、新シーズンもこのままトゥドルにチームの指揮を委ねる決断を下した。
トゥドルは現役時代にDF/MFとしてユベントスでプレーしただけでなく、20-21シーズンにはアンドレア・ピルロ監督の副官として1シーズンを過ごしており、クラブの環境は十分に理解している。監督としてヴェローナ、マルセイユ、ラツィオなどで示してきた戦術的な志向性は、今やイタリア・サッカー界で一大派閥となりつつある「ガスペリーニ派」、つまりジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の影響を強く受けたスタイルだ。
特徴を具体的に列挙するなら、3バックとフラットな4MFによる中盤、3人のアタッカーという構成を基本に、ハイプレス時はもちろん相手のポゼッションに対してもミドルサードから上ではマンツーマンで相手を捕まえるデュエル志向のアグレッシブな守備、中央レーンをあまり使わずサイドでローテーションを多用しながらパスをつないで前進し、ゴール前に多くの人数を送り込んでクロスを軸に決定機を作り出す攻撃、ということになるだろうか。
これは、前監督のT・モッタが打ち出していた4バックのシステムを基本に、守備はミドルプレス主体のゾーンディフェンス、攻撃は後方からのビルドアップとポゼッションでボールを支配して主導権を握るスタイルとは、ベースとなる哲学のところから異なるサッカーである。
とはいえ、トゥドルは23-24シーズン、やはり前任のマウリツィオ・サッリがまったく毛色の違うサッカーをしていたラツィオに途中就任し、短期間で自身のスタイルをチームに定着させてポジティブな結果を残した実績がある(サッリの下でくすぶっていた鎌田大地が突然躍動したのも記憶に新しい)。ユベントスでも3月半ばに途中就任すると限られた時間でチームを何とか形にし、ラスト9試合で勝点18を挙げて最低ノルマだったCL出場権を勝ち取っている。
このクラブW杯は「つなぎ」ではなく、新シーズンも引き続き指揮を執る「正監督」として臨む初めての舞台になった。チームの陣容も、基本的にシーズン中から大きな変化はなし。レンタル加入だったCBレナト・ヴェイガがチェルシーに戻り、レンタルに出ていたCBダニエレ・ルガーニと左WBフィリップ・コスティッチが復帰したのを除くと、この大会限定でレンタルを延長したCFランダル・コロ・ムアニ、右WGフランシスコ・コンセイソンを含めて「23-24仕様」であり、この点は「24-25仕様」に近いインテルと少し異なるところだ。
GSの成績は2勝1敗。グループGは典型的な「2強2弱」の構成で、アル・アインとの初戦は5-0、ウィダードとの第2戦は4-1と、いずれも文字通りの楽勝だった。ボール支配率はいずれも60%強。その中で、サイドCB、WB、セントラルMF、トップ下(シャドー)の4人がサイドの2レーンを使い流動的にポジションを入れ替えながら1タッチ、2タッチでボールを動かして前進するビルドアップ、その流れの中でアタッキングサードにまで進出してフィニッシュにも絡むCBの攻撃参加、ゴール前に4~5人を送り込むファイナルサード攻略、そしてマンツーマンで前から人を捉まえて行くディフェンスといった、トゥドルが掲げるサッカーの主要なプレー原則がスムーズに機能していたのは、ひとつの収穫と言えるだろう。
ただし、マンチェスター・Cとの第3戦では、チームとしての戦術的な完成度、個の絶対的なクオリティーの両面で、欧州トップレベルとの格差をまざまざと見せつけられる結果になった。2-5のスコアはともかく、ボール支配率は25%止まり、アタッキングサードに限った支配率(フィールドティルト)はわずか9%、ボール奪取1回あたり相手に許したパス本数の平均値を示すPPDAは、マンチェスター・Cの6.5に対してユベントスは21.4という圧倒的な違い。パスを6本つなぐ間にボールを奪われ、それを取り返すまでに21本つながれている、と考えれば、ボール保持のクオリティーにどれだけの差があったかがわかるだろう。
ユベントスの2得点は、先制された直後の11分にGKのパスミスをカットして決めた、半ばプレゼントしてもらったようなゴールと、5-1と大勢が決して試合の強度が下がった84分、敵最終ラインのズレを見逃さずうまく裏に飛び出したドゥシャン・ヴラホビッチに、ケナン・ユルドゥズが絶妙な斜めのスルーパスを通して決まったゴール。後者は、この試合唯一と言っていいクリーンなビッグチャンスだった。全体としては、内容・結果ともに、現時点における両チームの実力差がそのまま反映された順当な試合だったと言うことができるだろう。
このユベントスをインテルと比較すると、後者は監督こそ変わったものの戦術的には継続性の強いサッカーを見せ、チームとしてのアイデンティティーがそれなりに確立されているのに対し、前者は3か月前に就任した監督が打ち出した戦術プロジェクトを少しずつ消化し、形にしている途上。その歩みはまずまず順調とはいえ、まだ明確なアイデンティティーを帯びるには至っていない、ということになるだろうか。
次のラウンド・オブ16では、早くも強敵レアル・マドリーとの対決が待ち受けている。相手も新監督の下でこれまでとは明らかに異なるタイプのサッカーに取り組んでいるが、個のクオリティーではやはり明らかな差があるだけに、ユベントスはマンチェスター・C戦同様に守勢に回る展開になりそう。どんな戦いになるかは興味深いところだ。
とはいえユベントスにとっては、インテルにとっても半ばそうであるのと同様、この大会は結果を追求する以上に、新監督の下での新たなプロジェクトの基盤を固める機会という意味合いが強い。2021年にセリエA連覇が9で途切れて以来、毎年のように「仕切り直し」を繰り返しながら、今なお新たなサイクルを定着させるに至っていない現状にピリオドを打つことこそ、クラブとして取り組むべき最も大きな課題であることは明白だ。
マドリー戦がどのような結果で終わるにしても、このクラブW杯はそうした観点に立って総括されるべき。そこから新シーズンに向けた明確なプロジェクトを導き出し、一丸となって推進する体制を確立できるかどうかが、今夏のユベントスをめぐる注目点と言えるだろう。
文●片野道郎
【記事】イタリア代表新監督ガットゥーゾは、「帰属意識」「結束」「ファミリー」を柱に「敵陣でボールを保持し、ゴールを奪うチーム」を目指す【現地発コラム】
【記事】イタリア代表が大混乱…前日解任のスパレッティ監督がチームを指揮→後任決まらずW杯1年前に指揮官不在の異例事態【現地発コラム】
トゥドルは現役時代にDF/MFとしてユベントスでプレーしただけでなく、20-21シーズンにはアンドレア・ピルロ監督の副官として1シーズンを過ごしており、クラブの環境は十分に理解している。監督としてヴェローナ、マルセイユ、ラツィオなどで示してきた戦術的な志向性は、今やイタリア・サッカー界で一大派閥となりつつある「ガスペリーニ派」、つまりジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の影響を強く受けたスタイルだ。
特徴を具体的に列挙するなら、3バックとフラットな4MFによる中盤、3人のアタッカーという構成を基本に、ハイプレス時はもちろん相手のポゼッションに対してもミドルサードから上ではマンツーマンで相手を捕まえるデュエル志向のアグレッシブな守備、中央レーンをあまり使わずサイドでローテーションを多用しながらパスをつないで前進し、ゴール前に多くの人数を送り込んでクロスを軸に決定機を作り出す攻撃、ということになるだろうか。
これは、前監督のT・モッタが打ち出していた4バックのシステムを基本に、守備はミドルプレス主体のゾーンディフェンス、攻撃は後方からのビルドアップとポゼッションでボールを支配して主導権を握るスタイルとは、ベースとなる哲学のところから異なるサッカーである。
とはいえ、トゥドルは23-24シーズン、やはり前任のマウリツィオ・サッリがまったく毛色の違うサッカーをしていたラツィオに途中就任し、短期間で自身のスタイルをチームに定着させてポジティブな結果を残した実績がある(サッリの下でくすぶっていた鎌田大地が突然躍動したのも記憶に新しい)。ユベントスでも3月半ばに途中就任すると限られた時間でチームを何とか形にし、ラスト9試合で勝点18を挙げて最低ノルマだったCL出場権を勝ち取っている。
このクラブW杯は「つなぎ」ではなく、新シーズンも引き続き指揮を執る「正監督」として臨む初めての舞台になった。チームの陣容も、基本的にシーズン中から大きな変化はなし。レンタル加入だったCBレナト・ヴェイガがチェルシーに戻り、レンタルに出ていたCBダニエレ・ルガーニと左WBフィリップ・コスティッチが復帰したのを除くと、この大会限定でレンタルを延長したCFランダル・コロ・ムアニ、右WGフランシスコ・コンセイソンを含めて「23-24仕様」であり、この点は「24-25仕様」に近いインテルと少し異なるところだ。
GSの成績は2勝1敗。グループGは典型的な「2強2弱」の構成で、アル・アインとの初戦は5-0、ウィダードとの第2戦は4-1と、いずれも文字通りの楽勝だった。ボール支配率はいずれも60%強。その中で、サイドCB、WB、セントラルMF、トップ下(シャドー)の4人がサイドの2レーンを使い流動的にポジションを入れ替えながら1タッチ、2タッチでボールを動かして前進するビルドアップ、その流れの中でアタッキングサードにまで進出してフィニッシュにも絡むCBの攻撃参加、ゴール前に4~5人を送り込むファイナルサード攻略、そしてマンツーマンで前から人を捉まえて行くディフェンスといった、トゥドルが掲げるサッカーの主要なプレー原則がスムーズに機能していたのは、ひとつの収穫と言えるだろう。
ただし、マンチェスター・Cとの第3戦では、チームとしての戦術的な完成度、個の絶対的なクオリティーの両面で、欧州トップレベルとの格差をまざまざと見せつけられる結果になった。2-5のスコアはともかく、ボール支配率は25%止まり、アタッキングサードに限った支配率(フィールドティルト)はわずか9%、ボール奪取1回あたり相手に許したパス本数の平均値を示すPPDAは、マンチェスター・Cの6.5に対してユベントスは21.4という圧倒的な違い。パスを6本つなぐ間にボールを奪われ、それを取り返すまでに21本つながれている、と考えれば、ボール保持のクオリティーにどれだけの差があったかがわかるだろう。
ユベントスの2得点は、先制された直後の11分にGKのパスミスをカットして決めた、半ばプレゼントしてもらったようなゴールと、5-1と大勢が決して試合の強度が下がった84分、敵最終ラインのズレを見逃さずうまく裏に飛び出したドゥシャン・ヴラホビッチに、ケナン・ユルドゥズが絶妙な斜めのスルーパスを通して決まったゴール。後者は、この試合唯一と言っていいクリーンなビッグチャンスだった。全体としては、内容・結果ともに、現時点における両チームの実力差がそのまま反映された順当な試合だったと言うことができるだろう。
このユベントスをインテルと比較すると、後者は監督こそ変わったものの戦術的には継続性の強いサッカーを見せ、チームとしてのアイデンティティーがそれなりに確立されているのに対し、前者は3か月前に就任した監督が打ち出した戦術プロジェクトを少しずつ消化し、形にしている途上。その歩みはまずまず順調とはいえ、まだ明確なアイデンティティーを帯びるには至っていない、ということになるだろうか。
次のラウンド・オブ16では、早くも強敵レアル・マドリーとの対決が待ち受けている。相手も新監督の下でこれまでとは明らかに異なるタイプのサッカーに取り組んでいるが、個のクオリティーではやはり明らかな差があるだけに、ユベントスはマンチェスター・C戦同様に守勢に回る展開になりそう。どんな戦いになるかは興味深いところだ。
とはいえユベントスにとっては、インテルにとっても半ばそうであるのと同様、この大会は結果を追求する以上に、新監督の下での新たなプロジェクトの基盤を固める機会という意味合いが強い。2021年にセリエA連覇が9で途切れて以来、毎年のように「仕切り直し」を繰り返しながら、今なお新たなサイクルを定着させるに至っていない現状にピリオドを打つことこそ、クラブとして取り組むべき最も大きな課題であることは明白だ。
マドリー戦がどのような結果で終わるにしても、このクラブW杯はそうした観点に立って総括されるべき。そこから新シーズンに向けた明確なプロジェクトを導き出し、一丸となって推進する体制を確立できるかどうかが、今夏のユベントスをめぐる注目点と言えるだろう。
文●片野道郎
【記事】イタリア代表新監督ガットゥーゾは、「帰属意識」「結束」「ファミリー」を柱に「敵陣でボールを保持し、ゴールを奪うチーム」を目指す【現地発コラム】
【記事】イタリア代表が大混乱…前日解任のスパレッティ監督がチームを指揮→後任決まらずW杯1年前に指揮官不在の異例事態【現地発コラム】
関連記事
- イタリア代表新監督ガットゥーゾは、「帰属意識」「結束」「ファミリー」を柱に「敵陣でボールを保持し、ゴールを奪うチーム」を目指す【現地発コラム】
- パリSGに0-5と歴史的大敗…圧倒的強度のプレッシングに「手も足も出なかった」インテル、「しかし、今シーズンの評価はむしろ…」【現地発コラム】
- 持てる力を限界まで絞り出した「コンテの手腕がナポリの“勝因”」2位インテルとの隔たりは「微妙な差」【現地発コラム】
- モッタ解任→トゥードル招聘、2億ユーロのプロジェクトに失敗したユベントス。夏の監督選びこそ「最後になるべき“再スタート”の始まり」【現地発コラム】
- 世界的観光地を本拠地とする“プロビンチャーレ”コモの野望――シティ、パリSGを上回る資産7.5兆円オーナーが目指す「サッカークラブの枠を大きく超えたビジネス」【現地発コラム】