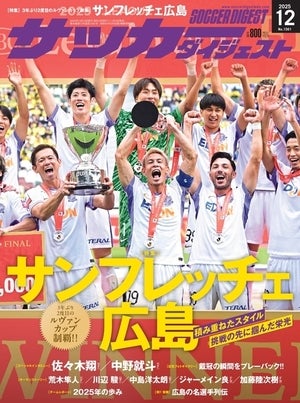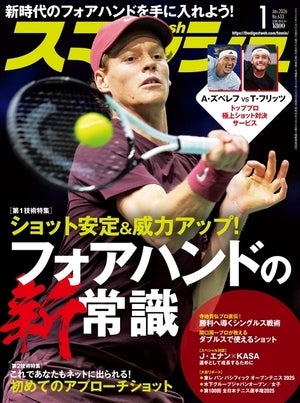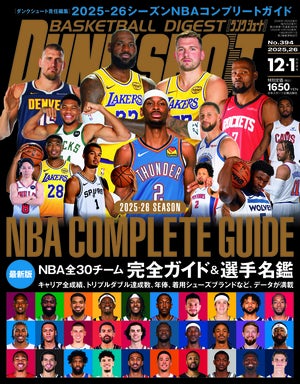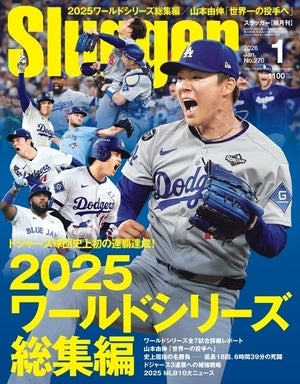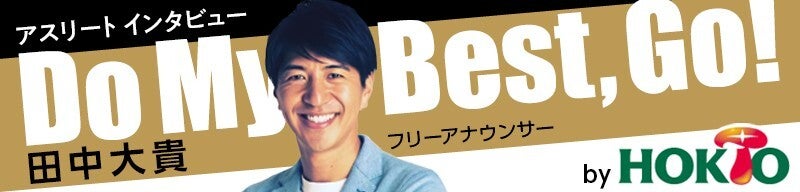第1レグ3ー3、第2レグは延長の末4ー3。どちらもインテルが2点リードした後バルセロナが2ー2に追いつき、そこからさらなる乱戦に雪崩れ込む派手でスリリングな展開だった。
この準決勝が近年のチャンピオンズリーグ(CL)史上稀に見る激戦となったのは、ある意味で「必然」だったと言うこともできる。得点経過までが同じになったのはさすがに偶然だろう。しかし、両チームの戦術スタイルの明確な違い、そしてその「噛み合わせ」からすれば、ゴールの応酬になる可能性は非常に高かった。それはどちらにも「失点する理由」が十分にあったからだ。
インテルがバイエルンに勝った準々決勝のレビューと準決勝展望の中で、筆者は次のように書いた。
「攻撃力という点から見れば、インテルはバルセロナに遠く及ばないことは明らかだ。しかし戦術スタイルという観点から見ると、バルセロナに対する「相性」はまったく悪くない。バルセロナは、相手を押し込んだ後のプレスの圧力、奪回の速さにおいては傑出しているが、一旦そのプレスを外されてハイラインの裏を衝かれた時には脆さを露呈するところがある。(中略)インテルにとってはまさにそこが格好の狙い目になるはずだ」
そして実際、この2試合を通じてインテルが挙げた7得点はすべて、何らかの形で「ハイラインの裏」が絡んだものだった。第1レグ開始直後の先制ゴールは、ロングボールの落としを右サイドに展開してデンゼル・ドゥムフリースが裏に抜け出したところから、残りの2得点はいずれもセットプレー(CK)からだが、そのCKは、2点目が裏への長いスローイン、3点目は自陣でのボール奪取からパス3本でやはりドゥムフリースが裏に抜け出したプレーから生まれたものだ。
第2レグも最初の2得点はいずれも、中盤でのボール奪取から素早く裏に送り込んだスルーパスがもたらしたもの(2点目は抜け出したFWラウタロ・マルティネスがCBパウ・クバルシのファウルを誘ってPK)。同点に追いついた後半ATの3点目、決勝点となった延長前半の4点目は、ロングボールに競り勝った落としを右サイドの裏に送り込んだところから生まれている。
この事実からも明らかなように、バルセロナの戦術には、極端なハイラインの裏を衝かれると非常に脆い「構造的な」弱点がある。そしてその弱点は、バルセロナが自ら「選んだ」ものだ。
攻撃時に陣形を敵陣まで押し上げるだけでなく、ボールを失っても後退することなくハイラインを維持して全体をコンパクトに保ち、ボールにプレッシャーをかけ続けることで相手に反撃を許さず、逆に高い位置でボールを奪い返して決定的なチャンスを作り出す。ハイラインの背後に残した広大なスペースはオフサイドトラップを駆使して守る――。
「ハイライン原理主義」とでも呼びたくなるようなこの守備戦術は、高いボール支配率によって守備の機会そのものを減らすと同時に、つねに敵ゴールに近いところで戦って攻撃力を最大化することを優先し、そのためにハイラインがもたらす「裏」のリスクは敢えて引き受けるという、きわめて自覚的な選択に基づくものだ。
1試合に何度か裏を取られて失点するときもあるだろうが、より多く得点すればいいだけのこと、我々にはそれだけの力がある、という「潔さ」の背景には、ヨハン・クライフの時代から40年に渡って受け継がれてきたクラブとしての哲学がある。この準決勝にバルセロナが敗れたのは、その哲学に「殉じた」がゆえと言うことすらできるかもしれない。
第2レグ後半の87分にラフィーニャが3対2とリードするゴールを決めた時点で、激戦に決着がついたかのように思われた。実際、もしこの時点でバルセロナがラインを下げて守勢に転じ、リードを守り切ることに専念していれば、その後に我々が目の当たりにした劇的なドラマが起こることはおそらくなかっただろう。インテルはすでに時計が1時間を回ったあたりからエネルギーが枯渇してきており、もはや反撃する余力などまったく残っていないように見えた。
しかしバルセロナはその後も攻撃の手を緩めず、ラインも下げなかった。92分にはラミネ・ヤマルが「とどめの一撃」にもなりえたゴールポスト直撃のシュートを放ってすらいる。だがそのわずか1分後、大きな代償を支払うことになった。
インテルのGKヤン・ゾマーが蹴り出したロングボールを競り合ったこぼれ球をマルキュス・テュラムに拾われ、ハーフウェイライン近くまで押し上げていたハイラインが背走を強いられた末に、ドゥムフリースのクロスを(なぜか前線に攻め上がっていたCBの)フランチェスコ・アチェルビに決められ、試合は土壇場で振り出しに。そして延長前半の99分に決まったダビデ・フラッテージの決勝ゴールもまた、GKからのロングボールに競り負けて裏を取られたところから生まれたものだった。
この準決勝が近年のチャンピオンズリーグ(CL)史上稀に見る激戦となったのは、ある意味で「必然」だったと言うこともできる。得点経過までが同じになったのはさすがに偶然だろう。しかし、両チームの戦術スタイルの明確な違い、そしてその「噛み合わせ」からすれば、ゴールの応酬になる可能性は非常に高かった。それはどちらにも「失点する理由」が十分にあったからだ。
インテルがバイエルンに勝った準々決勝のレビューと準決勝展望の中で、筆者は次のように書いた。
「攻撃力という点から見れば、インテルはバルセロナに遠く及ばないことは明らかだ。しかし戦術スタイルという観点から見ると、バルセロナに対する「相性」はまったく悪くない。バルセロナは、相手を押し込んだ後のプレスの圧力、奪回の速さにおいては傑出しているが、一旦そのプレスを外されてハイラインの裏を衝かれた時には脆さを露呈するところがある。(中略)インテルにとってはまさにそこが格好の狙い目になるはずだ」
そして実際、この2試合を通じてインテルが挙げた7得点はすべて、何らかの形で「ハイラインの裏」が絡んだものだった。第1レグ開始直後の先制ゴールは、ロングボールの落としを右サイドに展開してデンゼル・ドゥムフリースが裏に抜け出したところから、残りの2得点はいずれもセットプレー(CK)からだが、そのCKは、2点目が裏への長いスローイン、3点目は自陣でのボール奪取からパス3本でやはりドゥムフリースが裏に抜け出したプレーから生まれたものだ。
第2レグも最初の2得点はいずれも、中盤でのボール奪取から素早く裏に送り込んだスルーパスがもたらしたもの(2点目は抜け出したFWラウタロ・マルティネスがCBパウ・クバルシのファウルを誘ってPK)。同点に追いついた後半ATの3点目、決勝点となった延長前半の4点目は、ロングボールに競り勝った落としを右サイドの裏に送り込んだところから生まれている。
この事実からも明らかなように、バルセロナの戦術には、極端なハイラインの裏を衝かれると非常に脆い「構造的な」弱点がある。そしてその弱点は、バルセロナが自ら「選んだ」ものだ。
攻撃時に陣形を敵陣まで押し上げるだけでなく、ボールを失っても後退することなくハイラインを維持して全体をコンパクトに保ち、ボールにプレッシャーをかけ続けることで相手に反撃を許さず、逆に高い位置でボールを奪い返して決定的なチャンスを作り出す。ハイラインの背後に残した広大なスペースはオフサイドトラップを駆使して守る――。
「ハイライン原理主義」とでも呼びたくなるようなこの守備戦術は、高いボール支配率によって守備の機会そのものを減らすと同時に、つねに敵ゴールに近いところで戦って攻撃力を最大化することを優先し、そのためにハイラインがもたらす「裏」のリスクは敢えて引き受けるという、きわめて自覚的な選択に基づくものだ。
1試合に何度か裏を取られて失点するときもあるだろうが、より多く得点すればいいだけのこと、我々にはそれだけの力がある、という「潔さ」の背景には、ヨハン・クライフの時代から40年に渡って受け継がれてきたクラブとしての哲学がある。この準決勝にバルセロナが敗れたのは、その哲学に「殉じた」がゆえと言うことすらできるかもしれない。
第2レグ後半の87分にラフィーニャが3対2とリードするゴールを決めた時点で、激戦に決着がついたかのように思われた。実際、もしこの時点でバルセロナがラインを下げて守勢に転じ、リードを守り切ることに専念していれば、その後に我々が目の当たりにした劇的なドラマが起こることはおそらくなかっただろう。インテルはすでに時計が1時間を回ったあたりからエネルギーが枯渇してきており、もはや反撃する余力などまったく残っていないように見えた。
しかしバルセロナはその後も攻撃の手を緩めず、ラインも下げなかった。92分にはラミネ・ヤマルが「とどめの一撃」にもなりえたゴールポスト直撃のシュートを放ってすらいる。だがそのわずか1分後、大きな代償を支払うことになった。
インテルのGKヤン・ゾマーが蹴り出したロングボールを競り合ったこぼれ球をマルキュス・テュラムに拾われ、ハーフウェイライン近くまで押し上げていたハイラインが背走を強いられた末に、ドゥムフリースのクロスを(なぜか前線に攻め上がっていたCBの)フランチェスコ・アチェルビに決められ、試合は土壇場で振り出しに。そして延長前半の99分に決まったダビデ・フラッテージの決勝ゴールもまた、GKからのロングボールに競り負けて裏を取られたところから生まれたものだった。
関連記事
- 「サッカーというスポーツを、対立ではなく統合、闘争ではなく融和、戦争ではなく平和の象徴として位置付けた」ローマ教皇を追悼【現地発コラム】
- 「15年前の再現」を目指すインテル、CL4強の他チームにはない“強み”とは? 準決勝の相手バルサに対する戦術的相性は「まったく悪くない」【現地発コラム】
- モッタ解任→トゥードル招聘、2億ユーロのプロジェクトに失敗したユベントス。夏の監督選びこそ「最後になるべき“再スタート”の始まり」【現地発コラム】
- イタリア代表、NL準々決勝でドイツに敗戦も…「強豪国相手に戦術的な優位性を発揮する可能性が見えたことはポジティブ」【現地発コラム】
- “コントロール”を失わなかったインテルと、“軽率かつ重大な失態”のアタランタ。上位対決の分水嶺は「経験値の差」【現地発コラム】