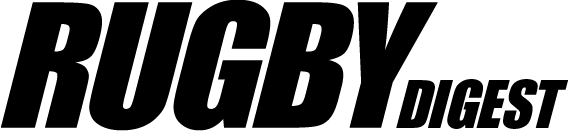サッカーの日韓ワールドカップから17年。当時の杓子定規で融通が利かない、しかめっ面のボランティアも、すっかり姿を消していた。「ボランティアが楽しまなくては、観客も楽しめない」。そんなマインドが、いつの間にかこの日本に浸透していた。
イングランド代表のエディー・ジョーンズHCは、南アフリカとの決勝戦を前に、「できればもっと長く日本にいたい」と話したが、きっと同じような想いは大会に参加したすべての国の選手、スタッフだけでなく、来日した多くの外国人サポーターも抱いてくれたに違いない。
もちろん、大会の価値と満足度を著しく高めたのが、日本代表チームの躍進であることは言うまでもないだろう。史上初のベスト8入りを果たしたあの快進撃がなければ、ラグビーというマイナースポーツに、これほど多くの日本人が夢中になることはなかったはずだし、もしかすると、こんなにも広い心で外国人サポーターを受け入れることもできなかったもしれない。
勝因を探せば、それこそいくつだって思い浮かぶ。
第一に、宮崎、網走でのかつてないほど厳しい合宿を経て、強豪国にも負けないフィジカルを身に付けたこと。アイルランドを倒した日、ベテランSHの田中史朗は言った。
「宮崎と網走での合宿がなければ、ここまでアイルランドを追い詰めることもできなかった。しんどいことをすれば(ティア1の)強いチームにも勝てるということを体現できた」
第2に戦略の勝利。緻密なスカウティングによって対戦相手を丸裸にし、自分たちの戦い方を柔軟に変える。ジェイミー・ジョセフHCの就任以来、ボックスキックを多用するアンストラクチャー(陣形が乱れた状態)からのアタックに一貫して取り組んできたが、本番ではそれに固執せず、ときにはポゼッションを重視し、ときにはあえて相手にボールを譲り渡した。いま思えば、キックへのこだわりはジョセフHCの巧妙な“撒き餌”ではなかったかと、勘繰りたくもなる。
イングランド代表のエディー・ジョーンズHCは、南アフリカとの決勝戦を前に、「できればもっと長く日本にいたい」と話したが、きっと同じような想いは大会に参加したすべての国の選手、スタッフだけでなく、来日した多くの外国人サポーターも抱いてくれたに違いない。
もちろん、大会の価値と満足度を著しく高めたのが、日本代表チームの躍進であることは言うまでもないだろう。史上初のベスト8入りを果たしたあの快進撃がなければ、ラグビーというマイナースポーツに、これほど多くの日本人が夢中になることはなかったはずだし、もしかすると、こんなにも広い心で外国人サポーターを受け入れることもできなかったもしれない。
勝因を探せば、それこそいくつだって思い浮かぶ。
第一に、宮崎、網走でのかつてないほど厳しい合宿を経て、強豪国にも負けないフィジカルを身に付けたこと。アイルランドを倒した日、ベテランSHの田中史朗は言った。
「宮崎と網走での合宿がなければ、ここまでアイルランドを追い詰めることもできなかった。しんどいことをすれば(ティア1の)強いチームにも勝てるということを体現できた」
第2に戦略の勝利。緻密なスカウティングによって対戦相手を丸裸にし、自分たちの戦い方を柔軟に変える。ジェイミー・ジョセフHCの就任以来、ボックスキックを多用するアンストラクチャー(陣形が乱れた状態)からのアタックに一貫して取り組んできたが、本番ではそれに固執せず、ときにはポゼッションを重視し、ときにはあえて相手にボールを譲り渡した。いま思えば、キックへのこだわりはジョセフHCの巧妙な“撒き餌”ではなかったかと、勘繰りたくもなる。